アフターパンデミックの反動か?それとも新たな無形資産か?なぜ今、社歌なのか
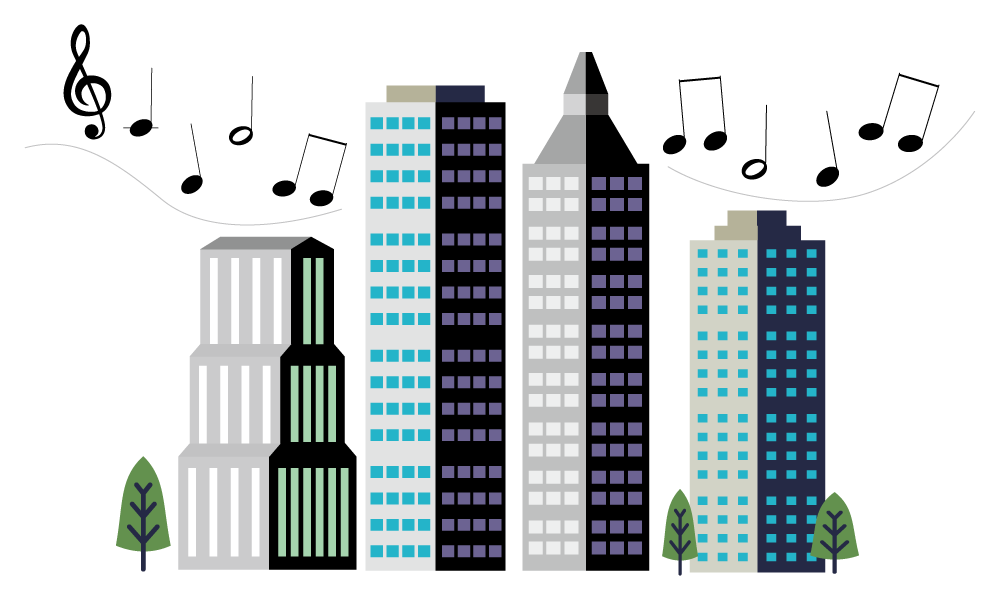
目次
■新型コロナパンデミックで、会社と社員の絆が弱まる
あなたの会社に社歌はあるだろうか?
「ない」としたら、会社のサステナブルな成長が危うくなるかもしれない─。それほど現代企業にとって重要な要素となっている。
大げさに聞こえるかもしれないが、イマドキの企業にとって社歌は社員のモチベーションアップや団結力、コミュニケーション向上に大きな役割を果たしているという。とくにこの数年は企業が社歌を制作する例が増えている。背景の1つには新型コロナのパンデミックがある。ステイホームが当たり前化し、会社という「箱」のなかで一緒に仕事をすることが少なくなり、社員同士のコミュニケーション、帰属意識、団結力、絆が弱まっていったのだ。
社員のコミュニケーション、帰属意識、団結力の低下は確実に組織を弱体化させる。とくに転職が当たり前化している現代においては、とりわけ若い世代が離職する格好の機会となりかねない。
そうした離職防止、やりがい、自己肯定感を高めるためにも社歌のニーズが高まっているというわけだ。
■社歌はサステナブルな経営を支える?
もちろんそれだけではない。実は1つ大きな仕掛けがあった。
2016年から始まった「社歌コンテスト」、通称「社歌コン」だ。社歌コンは広告代理店「電通」の社員が高校時代の甲子園出場経験を思い出し、その感動を企業人になっても味わうことができないかと考え、さらにその盛り上がりを企業のブランディングや社内コミュニケーションの活性化に活かせるのではないかと発案し、始まった。
コンテストは、応募企業の社歌動画についてWebの一般投票や審査員審査を実施。決勝進出12社を選定し、決勝戦を開催する。優勝社歌は、カラオケの「JOYSOUND」を通じて、全国に配信されることになっている。そして最初に新型コロナ報道がされた2019年には、日本経済新聞社が主催となり「NIKKEI社歌コンテスト」と名称が変わった。日経がついたことで俄然参加企業の熱も上がったが、そのタイミングでステイホームなどの行動規制が敷かれ、団結力や帰属意識が徐々に崩れていった。
■SNSや動画作成アプリなどで誰もが社歌クリエイターに
ほかにもSNSやYouTubeをはじめとする動画投稿サイトなどのメディアが発達し、動画を誰もが簡単に発信できる環境が整ったこと、専門家でなくても音楽制作ソフトやアプリを使って作詞作曲が可能となっていること、昭和歌謡などのレトロブームが続いていること、あるいはヒップホップなど、従来の協調にこだわらずとも社歌として認める空気が出てきたこともあるだろう。
社歌は一緒に歌うことや制作に関わることで団結力、モチベーション、帰属意識向上に貢献することができる。さらに歌詞に自社の特長や製品を織り込めば、PRやブランディングにもつながる。

■電話の保留メロディに社歌を流し、製品の認知度アップに貢献
たとえば、NTTデータは、2013年にグループの歌「NTT DATA One Song-Shine like the sun」を制作したが、この際、全社員を対象にしたアンケートを実施し、歌詞に込めたい思いやフレーズを募集した。それを同社の言語解析エンジン「なずきのおと」で解析・集計し、使っている。同社の社歌は日本語だけでなく英語版もあり、グローバルな親睦会などで歌われて、団結力や友好のきっかけとなっているという。さらに電話の保留時にこの社歌を流しており、そのなかで使われた「なずきのおと」の名称の認知度も上がってきているとのこと。
また食品大手のカゴメは120周年記念企画として、記念ソング「進めカゴメ」を創作。歌に合わせてノリノリのダンスを披露する総勢2400名の社員のプロモーションビデオを制作し、自社サイトや動画サイトで発信している。進めカゴメは、120周年記念に「全社が一体感を持ち、未来へ向かって成長していくカゴメを表現するにはどうすればよいか?」という問いのなかで生まれた歌で、厳密には社歌ではない。寺田直行社長が「企業理念と長期ビジョンを胸に、未来に向けて力強く歩んでいくための社歌に匹敵するような“私たち自身への応援歌”を作りたい」との発言から誕生している。歌詞に織り込むキーワードを“カゴメの好きなところ”などの従業員アンケートから選び、コピーライターの小藥元氏と歌詞を制作、「見る人にカゴメの成長性や元気を感じてほしい」との思いが伝わる、まさに自分たちへの応援歌となっており、確かに見る人に元気と働く喜びを感じさせる動画作品となっている。
■若手に社歌制作を任せて以後、右肩上がりの業績が続くロート製薬
「♪ロート、ロート、ロート♪…」の勢いのあるフレーズで知られる目薬シェアトップのロート製薬は、2004年に社歌「ハッピーサプライズよろこビックリの唄」を設定した。よく聞く冒頭のフレーズは、TVCM用のオープニングソングで、社歌ではない。新たに社歌を作った背景には、同社の山田邦雄社長(現会長)が若手に活躍の場を与えたいとの思いからだったという。山田社長は若手に次々とプロジェクトを任せたが、そのなかの1つが社歌を作るプロジェクトだった。「よろこビックリ」という言葉はロート製薬のコーポレートスローガンで、社歌にはこのスローガンに込めた同社の思いが表現されており、自分たちでつくった歌ということもあって、この社歌に鼓舞される若手も多いという。社歌を作って以降、同社の売上は右肩上がりが続いている。
■社歌動画により9年間で売上を4億円から25億円に引き上げた高知の食品会社
社歌は中小企業での効果が大きいようだ。高知県にある豆を使ったビスケットなどの加工食品を製造販売する有限会社野村煎豆加工では、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんが同社のためにデザインした「ミレーちゃん」というキャラクターが社歌に合わせてゆるく踊りながら会社を紹介するPVを制作したところ認知度が上がり、9年間で売上が4億円から25億円まで伸びたという。同社はこのPVのために社歌を創作しているが、キャラクターだけでなく、社歌もあったからこその効果とも言える。それにしても凄まじい効果だ。
■社歌は現代の無形資産となるか─
先の社歌コンによると、企業の社歌の利用法で多いのが、「動画にして企業PRに使う」で75.5%、「人材採用に活用」が41.5%という割合となっており、多くの企業が社歌を対外的なブランディングに活用していることが見て取れる(いずれも2023年)。
そしてこの社歌コンに参加した効果も絶大で、「顧客や取引先とのコミュニケーション増加」が最も大きく、62.8%、「社員とのコミュニケーション増加」が61.7%、「社員の統一感向上」が52.1%、「会社・商品・サービス認知の向上」が43.6%といずれも高い効果を発揮している。このほか「社員の生産性の向上」に9.6%、「人材採用に効果があった」とする企業が9.6%あった(いずれも2023年)。
コミュニケーションの活性化だけでなく、生産性や人材採用にも効果を発揮していることは、社歌が企業の無形資産の一部を形成していると言えるだろう。
■社歌ブームは戦前の第1次ブームから、今回で4回目
そもそも社歌ブームは今回に限ったことではなく、これまでもブームが起こっており、今回で4回目だ。
「社歌」の著作がある作家・ジャーナリストの弓狩匡純氏によれば、第1次ブームが起こったのは、第二次世界大戦前だ。
記録では、社歌が最初に作られたのは1917年。日本ではなく当時満州国に日本の国策として設立された南満州鉄道が社員の結束を強化する手段として歌詞を公募し、つくられた社歌「満鉄の歌」がそれである。以後、1900年代を通じて帰属意識と団結力を高めるツールとして企業が続々と社歌をつくっていった。とくに1930年の金融恐慌(昭和恐慌)以後は、会社の理念を共感させる手段として社歌制作が急増した。また第1次ブームの時には、朝礼や入社式など企業のイベントにからめて社歌が流れたり、歌うことが一般化した。
■終戦後の社歌ブームは、復興と喪失したアイデンティティ再構築のために
第2次ブームは戦後の復興期である。基本的に企業としての帰属意識や団結力を高める意味はあったが、戦後は喪失した日本人としてのアイデンティティを再構築する意味があった。同時に、復興という共通の目標に向かって協力姿勢を醸成する意義もあった。
この効果は、企業が落ち込んだり、再生に挑む際にも活用される。日本航空はかつて経営破綻した際、再生のための社歌「明日の風」を創作し、社員のモチベーションを牽引している。
第3次ブームは、高度経済成長期からバブル期にかけてだ。とくに70年代から80年代にかけては、都市部の住宅不足も解消し、日本が世界第2位の経済大国に躍り出た時代である。企業ではCIブームが起こり、ロゴマークやシンボルカラー、タグラインと呼ばれる企業活動のキャッチコピーが一新された。この文脈で社歌を創作または一新する企業が増えたのだ。その中身も、企業名を連呼するようなものから、心の豊かさやライフスタイルを表現するような歌詞内容が増え、また作曲も音楽大学の先生より、流行歌のヒットメーカーがつくることが多くなっていった。
そして近年の第4次ブームである。背景は冒頭に紹介した通りである。特長的なことは、専門家に依頼するより、社員が自分たちで作り上げるようになっていることだ。
コロナ禍を経て、運動会やスポーツ大会、社員旅行などを敢えて開催している企業が増えている。この10年ほどは、飲み会を嫌う若手社員が増えていたが、コロナ禍入社組のなかでは、懇親会や忘年会などに積極的に参加する若者も増えている。

■社歌ブームの背景に、デジタルネイティブ特有のコミュニケーションが…
こうした潮流に共通して見えてくるのは、1つの目的に向かって一緒に何かを作り上げる体験を欲しているということだ。従来スマホのインターフェイスを通じてしか「友達」になれないデジタルネイティブな人たちが、生身の人間とのコミュニケーションやコラボを求めているのかもしれない。
この生身の人間とのふれあい、コミュニケーションこそが、サステナブルな企業の資産なのかもしれない。
参考
【書籍】●『社歌』弓狩匡純[文藝春秋]
【WEB】●電通報 ● 朝日新聞デジタル ●日本経済新聞 ●テレビ東京 ● NHK ● itmedia ● R25 ●カゴメ ● NTT データ ●ロート製薬 ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム