いまさら必要?! 必要悪?!!いやいやAI時代だからこそ身につけたい「社内政治力」
「社内政治力」という言葉が注目を集めている。社内政治力というとどんなイメージを持つだろうか。アナログで属人的で、DXやAIがはびこる令和の時代には似つかないビジネススキル…。いまのビジネスには必要とされない過去の能力。あるいはそこはかとなくダーティな香りがする世界…。そんなイメージだろうか。しかしビジネス内容が複雑化、グローバル化し、関わる利害関係者が膨れ上がる現代においてこそ求められるビジネススキルだと言われている。
なぜいまこの古めかしい響きを持つ「社内政治力」が重要になっているのか。気になるその背景と活用法、そしてそのスキルを身につける方法を紐解いてみよう。

目次
■対立する利害を調整し、その目的を達成するために必要な力
社内政治力に限らず、政治という響きにはどこかダーティでアナログなイメージがつきまとう。しかしながらたとえば広辞苑を開いてみると「人間集団における秩序の形成と解体をめぐって、人が他者に対して、また他者と共に行う営み」とあったり、大辞泉では「ある社会の対立や利害を調整して社会全体を統合する」と説明されているように、社会集団の内部に生じる対立や紛争を調整し、秩序と安定を確保するために必要な営みの一つである。よって政治力とは、社会の秩序と安定を確保するために必要な調整力や紛争解決力を指すことになる。
会社においては、ある目的のために対立する利害を調整し、実行、実現に導く力と言える。「社内政治力の教科書」の著者で元リクルートの営業マンでコンサルタントの高城幸司さんによれば、社内政治力は一定の役職についた人には必ず求められる能力であり、必要悪ではなく実現のための武器であると言う。問題はその「調整力」がときに誹謗中傷を含んだ意見のぶつかり合いであったり、表に見える駆け引きではなく、裏に隠れた駆け引きや、関係者の間にある嫌悪感によって歪められてしまうことだ。
■同じデータや情報を見ても、立場や視点が違えば解釈や予測が変わる
生成AIが秒速で進化している現代にあっては、個人が持つ属人的データや情報を超える膨大なデータや情報を世界中からすぐ集めることができるため、説得材料には事欠かなくなってきた。AIがあれば、別に政治力を使わずとも最適な答えが導けるはずと思うのも当然だろう。しかし同じデータや情報を見ても立場や視点が違えば、解釈や予測も変わってくる。加えて昨今はそのデータが事実を反映しているか、フェイクか否かを判断する必要がある。
会社という組織の内側には常に対立する利害が存在するものだ。その対立は誰かが正しく、誰かが間違っているというわけではない。立場によって「正論」が違ってくるだけだ。
たとえば経営陣は利益の最大化を目指すことが最優先であるが、一般社員は働きがいを求める。開発部門は潤沢な予算を使ってクオリティを追求するが、経理部門は経費削減を求める。それぞれがそれぞれの理由で会社や仕事の理想を追求している。
さらに現代企業は社内だけでなく、外にも多様な利害関係者(ステークホルダー)を抱える。営業部門は顧客や見込み客の意見を反映しようとするし、調達部門やCSR部門は外部評価機関やNGO、行政の意見も反映する必要がある。経営陣は株主の要望にも応えなければならない。それぞれの部門は社内組織だけでなく、社外の利害関係者の意見も代表しているのである。
■働き方改革で高まる社内政治力
社内政治力が求められる背景には、そういった複雑化する利害関係の存在に加え、昨今の働き方改革がある。「社内政治力」の著者でマネジメントコンサルタントの芦屋広太さんによれば、働き方改革では労働時間ではなく成果主義で評価されるため、会社はより少ない時間で付加価値の高い仕事をするように求めてくるという。となれば新しい概念や技術など、いままでにない「新しい何か」が必要になる。しかしながら会社という組織は、とかくそれまでやっていたことを止めて新しい何かをすることに保守的な反応をする場合が多くある。「前例がない」「そんな新しいことがうまくいくわけがない」「失敗したらどうする?」などの理由をつけて、それを阻止しようとする。こうした障壁のもとになっているのが、企業内の派閥である。
派閥という言葉にはどうしてもネガティブな印象がつきまとう。確かに派閥活動がエスカレートすると、市場や消費者を向いた経営ではなく、派閥の利益を優先するようになり、既存事業の存在を脅かしたり、新規事業を妨害する工作が行われるなど、組織全体の利益を損なう事態を招くこともある。最悪派閥抗争が会社を消滅させることがある。
近年は若手を中心に派閥と距離を置く中立派や、派閥に関わらない孤高の存在を目指すビジネスパーソンが増えているようだが、高度成長時代はどんな小さな会社にも派閥があり、出世を目指すなら派閥に属するのが当たり前だった。
■「課長 島耕作」シリーズで増えた「脱派閥族」
この企業派閥のあり方に一石を投じたのが、1983年に連載が始まった青年漫画雑誌の『課長 島耕作』だった。主人公の島耕作は大手電機メーカー「初芝」の課長時代に、「出世したいなら、◯◯部長の派閥に入れ」と役員に誘われたにも関わらず、「私はどんな派閥にも属さない主義なのでお断りします」ときっぱりと断言。その後派閥争いの間で揉まれ、理不尽な異動にも負けず、一貫して中立派として戦い抜き、2008年にはついに社長まで登り詰め、『社長 島耕作』の連載をスタートさせたのである。
もちろん漫画だから描けたストーリーなのかもしれないが、作者の弘兼憲史さん自身が大手電機メーカー出身ということもあり、そのリアリティは群を抜いていた。この作品がビジネスパーソンに与えた影響は大きく、企業内の派閥政治と距離を置く若手社員が増えたことは確かだった。出世競争に明け暮れるというビジネスパーソンは徐々に減り、仕事より自分の家族や趣味を優先する人も増えていった。
会社だけでなく、国政の世界でも派閥解消が強く叫ばれるようになり、実際に自民党の主要な派閥はなくなっている。
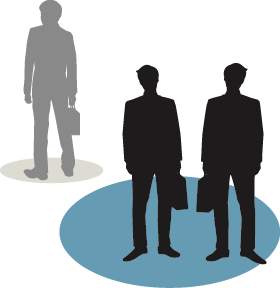
■派閥の存在を認めたうえで、和を生むリーダーシップを培う
しかしながら、「脱派閥を正義と捉えるのはいささか危険ではないか」と高城さんは考えている。なぜなら3人集まれば派閥が生まれるからだ。そもそも人間は群れる生き物。親近感のある人と繋がりを深めたい。仲間を増やして集団内での居場所を確保したい。あるいは強い力の庇護に入って安全を確保したいというのも、人間の本能に根ざした考えだ。派閥は自然現象なのだ。だとすれば、派閥の存在を認めてそれを活用するという方法が理にかなっている。
経営の神様と呼ばれたパナソニックの創業者、松下幸之助さんも『指導者の条件』のなかで「派閥を作るのは人間の本質」とその存在を認めた上で、「派閥は活用、善用すべきだと思う」と述べている。
派閥を全く否定するのではなく、自分の考え方を決めて近い派閥と情報を交換しながらその姿を常に俯瞰し、「和」を生み出すリーダーシップを涵養するのだ。
■社内政治力とは「他人からYESを引き出す能力」
派閥の力学を超えて、自分の案を実現していくためにも社内政治力が必要となる。社内政治力は目的のために対立する利害を調整し、その目的を実行、実現に導く力と述べたが、それは換言すると「影響力」である。
影響力と言えば、社会心理学者のロバート・チャルディーニが著した「影響力の武器」が有名だ。チャルディーニはこのなかで影響力を「他人からイエスを引き出す能力」と表している。自分の目指す方向へと相手に自発的に動いてもらうように促す力である。
もちろん入社して間もない時間では社内政治力は身につかないし、出世も望まないから社内政治力は必要ないと割り切っている人もいるだろう。しかし人は変わるものだ。

■社内政治力は、いまは必要なくても突然必要となる時がやってくる
いま社内政治力は不要だと考えている人も、5年先、10年先も同じ考えで会社員生活を送っているとは限らない。
高城さんは、社内政治力に関心を示さず、残業もほとんどしないような若手社員ががらりと変わる例をいくつも見てきたという。
会社に在籍する時間が長くなるにつれ、「自分がやってみたい」と思うことが見つかったり、「自分が立案したプランを通したい」といった気持ちが高まるときがあるからだ。
理由はいろいろだ。単純に仕事に欲が出たり、面白さを感じるようになったからかもしれないし、結婚して子供ができた、あるいは親の面倒を見なければならなくなったなど、プライベートのライフステージが変わったからかもしれない。上司が転職や転籍でいなくなり、それまでなかった権限が与えられたのかもしれない。
高城さんはリクルート時代、課長、部長、役員と役職が昇っていくにつれて、やりたいことを実現していくためには、この政治力が必要だと痛感していったと言う。
■役職を持たない人でも社内政治力は必要
会社組織において部下を持つ役職者の仕事は人を動かすことだ。そのための権限が与えられているが、権限には強制力を伴うだけに反発や摩擦を生み出しがちだし、また役職者の権限にはそれぞれ限界がある。大きなプロジェクトでは与えられた権限の行使だけでは、目的を達成できない可能性もある。部下を動かすだけでなく、上司を動かし、組織を動かすことによって、役職者としての成果を生み出していくことが求められる。つまり、大なり小なり組織を率いる者には社内政治力が必要なのだ。
役職を持たない人でも社内政治力は必要となってくる。
たとえば、営業先で担当者の理解を得、商品の見積もりを承諾してもらったと思ったら、なぜか契約までいかなかったとか、プレゼンの反応が良く、担当者から「進めてほしい」と言われて意気揚々と上司に報告したが、なぜか仕事自体は別の社に取られてしまった、といった経験はないだろうか。
こういった場合、相手の会社や組織が置かれている経済環境、経営環境の影響も大きいが、それ以外に担当者とその上の上司のソリが合わなかったり、担当者の上司が他の部署との承認を得られなかったなど、相手と周りの社員との関係性が大きな影響を与える場合が多い。端的に言えばビジネスは常に正論や正義が通るわけでも、合理的判断がなされるわけでもないということだ。
こんなことを言うと、「かと言って相手の会社の人間関係や社内政治までなんて、分かるはずないじゃないか!」と思う人もいるだろう。
しかし、高城さんによれば、たとえ相手の会社の人間関係や社内政治力学を知らずとも、その会社ではどんな人たちが権限を持ち、影響力を持っているのかがある程度わかるのだという。
■相手の会社のパワーバランスとキーパーソンは組織図と社史から読み解く
それが会社の組織図だ。会社組織図は会社の指示命令系と権限の所在を図面に落としたもの。つまりその会社で物事が決まっていく秩序が表現されている、いわば「海図」のようなものだ。
そして、そこの結節線にある人たちが、その事業や部門の権限を持つキーパーソンである。前述したように会社では権限を持った人がものごとを動かしていく。その権限には段階があり、金銭が関わることにはその権限の範囲内で決裁したり、プロジェクト推進の判断がなされる。しかしながら自分がやりたい、進めるべきだと思うような案件やプロジェクトについては、その権限を超えるため、こうしたキーパーソンの理解と協力が欠かせない。
社内政治力というビジネスパワーを最大化するためには、この組織図という海図にキーパーソンをマッピングしていくことが必要だ。高城さんはこの行為を「海図の上に気象図を描く」と表現する。取引先や商談先の背景にある大海原の波や風雨を予測して最適なビジネス進路を取るための進路図を描くイメージだ。
注意しなければならないのは、キーパーソンが必ずしも組織上に的確に現れているわけではないということだ。役職とは関係がなかったり、同じように見えても権限が与えられている人、そうでない人がいる。組織図を見る際に意識すべきは、会社にはその会社特有のパワーバランスがあるということである。一般的に会社内におけるパワーの指標となるのは、①人事権、②予算、③人員数である。このうち、最も影響があるのが左遷や解任、解雇の権限を持つ人事権だが、誰が人事に影響を与えるかを外から探るのは難しい。外から見えやすいのは予算と人員数だ。とくに人員数は単純に勢力や予算規模がわかるので、予算や人事権などにも強い影響があると推察しやすい。
もう1つパワーバランスを知るために高城さんが勧めるのは、その会社の社史を見ておくこと。するとそこでは、創業時の祖業やそこから発展分化していった事業などの歴史がわかってくる。時代によって栄枯盛衰があり、途中で撤退した事業や売却した事業も出てくる。詳細な社史では事業拡大や撤退、ヒット商品の開発者などのより具体的な情報が得られ、現在に至るパワーバランスの系譜が読める。最近は合併や売却などが積極的に行われているが、合併時どちらが主導したか、あるいは名称の残し方などからもパワーバランスがわかる。また赤字が続いていたり、売上規模が少ないにもかかわらず、事業を残していたりする場合は、その部署には脈々としたパワーの源泉があると考えていい。
たとえば鉄道会社などの場合、鉄道事業自体が今後拡大することは難しいと思われる。そのため、こうした鉄道会社は所有する土地を利用した不動産事業や小売り業などさまざまな事業を展開し、人員も予算も拡大させていることが多い。場合によっては鉄道事業自体は赤字に陥っていたりする。しかしながらこうした歴史を持つ鉄道会社において、鉄道事業部門の役員のパワーが削がれることはまずないだろう。
また社内行事もパワーの源泉を見る上で参考になる。たとえば一般に営業部門では月ごとの予算達成者を表彰したり、MVPとして報奨金を出したりしているが、製造業では現場を中心に、改善や技能に関する独自のコンテストが行われていたりする。その会社にとってどんな事業領域が重視されているかが社内行事からも見えてくるのだ。

■社内政治力の重要要素、ネットワークと情報解析力
キーパーソンを知る際に意識すべきは、誰がその部門における意思決定者の信頼を勝ち得ているかという観点だ。キーパーソンが意思決定をする際に必ず相談する相手がいれば、その人が実質的なキーパーソンであることも多い。いわゆるご意見番的な存在だ。こうしたご意見番には、いわゆる社歴の長い女性がなっているケースも多い。高城さんによれば男女格差がある日本の中で、こうした女性はパワーゲームに参加してこなかったが、それが故に中立的な立場を維持し、社内横断的な情報を維持している可能性が高いという。
グループ会社を持つ大きな事業会社の場合は、キーパーソンが本社を外れてグループ会社や子会社の中にいる場合もある。キーパーソンを知るためには人事異動を注視することもポイントだ。役員が代わったとき、新役員の出身部門が新たなパワーラインになった可能性は高い。
こうした視点によって培われた社内政治力は、自社で大いに活用できる。
ではその社内政治力を高めるためにはどのような要素が必要となってくるのか。
1つ目はネットワークである。社内はもちろん社外にもネットワークを広げておくべきだ。ネットワークを広げるためには、部署内だけでなく他部署との接点を広げることが重要で、社内政治力はすなわち影響力であるから、影響力を強化するには、さまざまな機会を通じて他部署、他社の人たちとのネットワークを構築する必要がある。ネットワークは相手に影響力を与える信号の発信網であるから、ネットワーク構築の際は、どの線がどこに繋がり、どのような効果が期待できるかを意識することが大切だ。社内政治力の達人ともなれば、ネットワーク構築に注意を払い「どうすれば困難な課題であってもサポートが得られるのか」「交渉をスムーズに進めるためには誰とつながっておくべきなのか」「余分な争いを避けるには誰に最初に話を持って行くべきなのか」など、有益な関係性を常に構築・維持している。
若い時にはどうやって社内のネットワークをつくっていくのか悩むに違いない。高城さんが提案するのは、花見会やスポーツ大会など社内イベントの幹事などに手を挙げることだ。社内イベントでは必然的に他部署の社員と接点を持たざるを得ないので、その際、相手の業務内容や課題などをさり気なく聞いておくといいだろう。
2つ目は、情報力である。情報は現代のビジネスにおいて重要なことは言うまでもない。インターネットを使えば必要な情報が集まる時代だ。だが政治力を高めるためには、表に出ているフォーマルな情報だけでは不十分だ。インフォーマルな情報をどれだけ取れるかが重要となる。そのためには1つ目のネットワークを広げることが大事となるが、そのネットワーク網が良質であることが大切となることは言うまでもない。

■「問題意識」が情報感度を高める
情報力を高めるためには、重要な情報かどうか、今後相手や相手の部署、会社がどのように変化するのかという「兆し」を察知・判断できるようにすることも大切だ。そのためには常に情報感度を高めておく必要がある。
感度というと持って生まれたセンスとも思われそうだが、ビジネスパーソンが感度を高める基本は「問題意識を持つ」ことである。「会社はどこに向かおうとしているのか」「自分の部署にとっていまなにが求められているのか」「この上司は何を気にしているのか」「取引先の担当者の部署にとって一番欲しいものは何か」といった問いだ。この問題意識が明確であれば、情報の質を嗅ぎ分けるセンスが身についていく。とくに会社の経営方針や経営計画、人事情報、売上や利益率に関する情報は、社内政治力の効果に差を生むようになる。
3つ目は、分析力だ。たとえば誰かに何かを相談したり、提言する際には得た情報から分析し相談内容、提言内容を整理しておく必要がある。
さらに4つ目として、その相談内容や提言内容をどこまで出すべきかを熟考する必要がある。相談を持ちかける相手が、その内容をもとに自分の提案にアレンジして手柄を自分のものにしないとも限らないし、それほど重要な提案だとも思わないかもしれない。相手に期待する反応を想定し、どこまで開示するかを見極める思慮深さが求められる。
5つ目は、計画の遂行力だ。会社は経営層が練り上げた経営計画や事業計画がそれぞれの権限者に落とし込まれて動くようになっている。それは一般社員にもある。それぞれの社員に落とし込まれた計画をしっかりクリアできるかがポイントになる。つまり確実に実績を積むということだ。ただ社内政治力は周りの人、部門間を超えた人や上司に対する影響力である。そのため社内政治力を引き上げていくためには、与えられた仕事をクリアするだけでなく、予算を持ったプロジェクトを発案し、そのリーダーとして結果を残すことも重要だ。
ある人事系コンサルティング会社の調査によれば、会社に入ってトップまで上り詰めた人に多かったのは、権限に応じた業務で目標以上の実績を残すだけでなく、キャリアの途中であえて小さめのプロジェクトに参加し、そのリーダーとして結果を残した人だったという。
こうした能力やスキルは一朝一夕に身につくものではない。まして入社間もない若手にとっては眼の前の仕事をこなすだけで精一杯となろう。そんな若手に対して高城さん
は、「入社1、2年目の頃は仕事を覚えること」が優先と諭す。「自分が会社でやりたいことがわからないうちに、せっせと異業種交流会などに参加して人脈を広げるより、仕事をしっかりしたほうがいい」(高城さん)。
■社内政治力をつけるための基盤「信頼の貯金」
そういった新人が社内政治力をつける上で重要になってくるのが、その基盤づくりである。いわば社内政治力を発揮するためのインフラである。
そのインフラの基本となるのが周りからの信頼である。信頼を得るためにはどうすればいいか。それは常に誠実であることだ。
具体的には、①礼儀正しくする、②謙虚である、③嘘をつかない、④約束やルールを守る、⑤誰とでも分け隔てなく接する、⑥人によって態度を変えない、⑦人の話には素直に耳を傾ける、⑧間違った時には謝る、である。いずれもビジネスパーソンというより、人としての基本だ。高城さんは、この基本を忠実に守り続けることが重要だという。
当たり前だが、全てのビジネスパーソンは顧客のニーズに応え、社会と調和しながら会社に貢献することが求められている。これはあらゆる仕事の基本だが仕事をしていれば失敗することはある。そして失敗すれば信頼は傷つく。そんな時に自分を守ってくるのは「信頼の貯金」だという。貯金がしっかり貯まっていれば、1回程度の失敗で信頼の貯金が底をつくようなことはない。致命的な失敗でなければ迷惑を被った人々も許してくれるはずだ。
もしかしたらその失敗を問題視する勢力がいるかもしれない。しかし貯金が貯まっていれば、信頼を寄せる人々がその対抗勢力になってくれる。「だから社内政治は長期戦です」(高城さん)。信頼インフラをしっかり作った人が、長期的には勝つのである。
■信頼の貯金の第一歩「あいさつ」
ベースとなる信頼の貯金づくりで、忘れてはならないのが「あいさつ」である。あいさつをしないということは、相手に対して「あなたはあいさつするほど私にとって重要な存在ではない」というサインを送っているのに等しい。また呼びかける際には名前で呼ぶことも大切だ。人間はどんな言葉をかけられた時にもっとも喜びを感じるかを調査する心理実験がある。直感的に「ありがとう」「すごいね」などの感謝や賛辞の言葉だろうと思われたが、一番は本人の名前だったという。
人間は関心のない人の名前を覚えようとはしないのだ。つまり名前を覚えているかどうかは、相手が自分という存在をどう捉えているかを図る尺度でもあるのだ。
実際出世する人のほとんどは名前で呼びかけるという調査結果もある。大企業の役員まで勤め上げたある人は、課長時代から上層部はもちろん、直属の部下から関係部署の新人まで、名前とそのプロフィールを手帳にメモをして全て覚えるように努力していたという。
彼は「まだ会社に馴染めていない新人に名前で呼びかけると、100%顔を輝かせますよ。そして僕のファンになってくれる」と断言している。
さらに声をかける際は、できる限り個別具体的な話題を投げかけるのも効果的だ。たとえば朝、出社する部下に挨拶するだけでなく、「◯◯さん、昨日の打ち合わせどうだったかな?」「確か、今週末は家族旅行だったよね。天気は大丈夫なんだっけ?」など、その人ならではの話題を投げかけるといい。単に「調子はどう?」「今日も頼むよ」などといった声がけをする人もいるが、これだけでは効果は薄い。
■相手の話を聞くときは、相手に正対して臨む
「聞き上手」であることも重要だ。相手の話に耳を傾けることは、相手に対する敬意を示すことでもある。傾聴の重要性はビジネス界のあちこちで語られているが、話を聞く際には相手に対して正面から向き合う姿勢をとることが大事だ。仮にすぐ相談を受けられない場合は、一旦その姿勢を取った上で、「いま手が離せないので、後で声をかけていいですか?」と言うと、相手の自尊心を傷つけることはない。つまり話は聞けないが、「あなたの話は聞くに値します」というメッセージを添えることになる。相手は「自分の価値を認められた」「褒められた」と思い、あなたに対する信頼度を増すことになる。
話を聞く時に注意したいのが、相手の話を途中で遮ることだ。相手からすると自分の価値を貶められたと気づいて、心の中で反発を強めている可能性もある。
信頼を得るには、態度だけでなく実績も重要だ。圧倒的な実績を上げてきた人物とそうでない人物とでは発言力に差が生まれるからだ。
このほか、希少性のある専門知識も信頼度を高めてくれる。「この分野のことならあの人」という存在になれば、強い発言力を持つことはもとより、組織内であなたの存在を大切にしようという力学も働くようになる。
■社内政治力行使の初手「根回し」
社内政治力はこれらの「信頼インフラ」を構築し、社内政治力の要素を押さえたうえで、慎重に行使する。行使の際にまず取り組むべきは、「根回し」だ。
プロジェクトや案件の決裁、Goサインをもらう時には、上述したキーパーソンに対して根回しをしておく。根回しという言葉もどこかダーティで古めかしいイメージがつきまとうが、利害関係者が多い事案において根回しは、決定や決裁をスムーズにする上で不可欠な行為だと言える。
たとえば新製品を開発したいなら、開発部門や設計部門にできそうかどうかの可能性を探っておくべきだし、実際に開発となれば、どれぐらいの予算が要るのか、その予算の満額を引き出せるのか。特許などの法的な権利はクリアできるのか、開発ステージによってどのくらいの人材が必要になるかなど、各担当部門のキーパーソンに聞いておくことが必要となる。社内に十分なリソースがない場合は、社外に求める場合もある。根回しはプロジェクト実現のための事前のヒアリングであり、自分や自分の部署に欠けているリソースを的確に探る意味でも重要なのである。
またこの根回しを行うことで、どの部署のキーパーソンが反対しているかや、反対理由なども見えてくる。
■「会社でやりたいこと」を実現するには主語を変えよ
前述したように、会社にはさまざまな抵抗勢力が存在する。その抵抗勢力のNOをYESに変える力が社内政治力だが、間違っても社内政治力ですべてをYESに変えようとは思わないことだ。
社内政治力がついたからといってオセロのように黒が一気に白に変わったりはしないもの。新規提案やプランを実行に持っていく、または決裁に持っていくためには6割から7割の支持で十分だということだ。51対49でもプランは遂行できる。
この比率は実際の多数決の人数を意味するものではない。人間の心理状態を言っている。つまり、どんな提案でも部署や会社のことを思って立案されたものであれば、まったく否定されるものではないということ。表向き否定していても、内容の2割なり、1割なりは賛同する部分はあるものだ。社内政治力はその少ない比率の壁を押しやって広げていく力である。そこに刺さるポイントや要素があれば、賛同部分はたちまち広がる。
賛同者、支援者を増やし、NOをYESに変えていく最も有効な方法は、何か。それは主語を変えることだ。
「会社でやりたいこと」が「私」が主語だったら、自分の保身や出世のためだと思われ、賛同者や協力者は現れないだろう。しかし主語を「我々」に変えれば、賛同者、協力者は増えていく。「自分の利益」だけではなく、「チームの利益」「会社の利益」とその主語の範囲を広げ、多くの人を巻き込む形に持っていけば、やりたいことは実現に近づいていく。
「社内政治力」の著者の芦屋広太さんは、社内政治力は、身につけた人の仕事の自由度を上げていく、という。
いまその必要性を感じていない人でも、いつか「いまの会社で実現したい」ことができた時のために、準備しておいて損はないだろう。
参考
【書籍】●『上司も部下も思い通りに動かす社内政治力』芦屋広太[フォレスト出版]●『「課長」から始める社内政治の教科書』高城幸司[ダイヤモンド社]ほか
【動画】●社内政治に絶対負けない法~権力アップの五大源泉とは[MBAの三冠王チャンネル]●影響力のある社員になる、組織図から反対派を見つける、キーパーソンは人事にあり、将来のための社内政治、心の余裕を見せて情報を集める[PIVOT TALK] ●社内政治を下手な人が知らない2つの技術[上場の法則] ●自由に生きるための5つの権力獲得戦略〜社内政治力を身につける科学[メンタリストDaiGo] ほか
【WEB】●マイナビ● INVENIO ● Schoo for business ●武蔵野コラム●日本の人事部 ほか
POINT
■ 社内政治力とは対立する利害を調整し、その目的を達成するために必要な力
■ 同じデータや情報を見ても、立場や視点が違えば解釈や予測が変わる
■「課長 島耕作」シリーズで増えた「脱派閥族」
■ 派閥は生まれる。認めて善用する
■ 働き方改革で高まる社内政治力
■ 相手の会社のパワーバランスとキーパーソンは組織図と社史から読み解く
■ 役職を持たない人でも社内政治力は必要
■ 社内政治力の重要要素、ネットワークと情報解析力
■「問題意識」が情報感度を高める
■ 社内政治力の行使では内容をどこまで出すべきかを熟考する
■ 社内政治力をつけるための基盤「信頼の貯金」
■ 信頼の貯金の第一歩「あいさつ」
■ 相手の話を聞くときは、相手に正対して臨む
■ 社内政治力行使の初手「根回し」
■「会社でやりたいこと」を実現するには主語を変えよ
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム