人材不足時代に効果バツグン!社員全員で取り組める「絵本を使ったマネジメント」研修
近年個人の成長、組織の活性化にアート思考を取り入れる企業が増えている。アートを理解する、あるいは理解しようとすることは、脳の活動領域を広げることがわかっており、導入の効果は計り知れない。しかしながら複雑に分化した現代アートを理解するには、それなりのセンスと時間が必要だ。アート思考を取り入れる前に、もっと身近でわかりやすい美術作品を用いた組織活性化ができないものか……。そんなニーズに応えてくれそうなのが、「絵本を使ったマネジメント」研修である。絵本でマネジメントが学べるものなのかと疑問をもってしまうが、絵本には大人となった今だからこそ、学べることがたくさんある。

目次
- ■欧米では絵画とともに「図像解釈学」が発展した
- ■現代人の祖先、ホモ・サピエンスが生き残れたのは、美を理解していたから
- ■現代アートを理解する脳と苦手な脳がある
- ■コミュニケーションは言語より視覚情報のほうが伝わる
- ■絵本を読み解くことで、その組織の課題がわかり、解決策が見い出せる
- ■人材不足が恒常化している今、取り入れたい絵本を使ったマネジメント研修
- ■ロシアの絵本『おおきなかぶ』が変えた社歴60年の企業風土
- ■絵本にある物語の空間を埋める人や環境から表情や感情を読み解く
- ■生産性の阻害要因は何かを学ぶカナダの『せかせかビーバーさん』
- ■「見える化」について考えさせるドイツの絵本『たのしいおかたづけ』
- ■イノベーションのきっかけを与えるアメリカの『ながーい5ふん みじかい5ふん』
- ■個性の引き出し方とリーダーシップを学ぶアメリカの『スイミー』
■欧米では絵画とともに「図像解釈学」が発展した
複雑化、曖昧化、激変する時代の課題解決手法として、アート思考がかねてより注目されている。ビジネスパーソンの間では、手法としてのアートのほかに、教養としてのアートが広がっている。これは欧米のエリート教育においては、哲学に代表されるような美意識の育成が重んじられてきた歴史があることに由来する。
たとえば、古くから多くの政治家を輩出しているイギリスのオックスフォード大学の看板は、今でも哲学、政治、経済学科であるし、フランスでも大学入試資格となる共通試験「バカロレア」においは、文系理系を問わず、最重要な必須教養として哲学が位置づけられている。これはエリートには大きな権力が与えられるため、哲学を学ばないエリートは権力を私物化し、政治や組織における専横や暴走を招きかねないという考えによるものだ。
美術史、美学をエリートの教養の前提としている欧米において、美術は鑑賞するものではなく、読み解くものだと認識されている。これにはとくに絵画を発展させてきたキリスト教の影響が大きい。というよりキリスト教のために西洋絵画が生まれたといっても過言ではない。民衆の大半が文字を読めなかった時代、キリスト教の教義を理解させるには、絵画ほどわかりやすいものはなかったからだ。よって欧米では、美術解読が学問として進んだのである。絵画では「図像解釈学=イコノロジー」として発展した。
■現代人の祖先、ホモ・サピエンスが生き残れたのは、美を理解していたから
日本は世界で稀に見る美術館大国、美術展大国である。にもかかわらず観覧者がただ「綺麗」「面白い」といった鑑賞レベルにとどまっているとしたら、実にもったいないことだ。もったいないというのは、美意識を高めることは世界でビジネスを展開する現代ビジネスパーソンの必須教養であることのみならず、人間集団が集団として生き延びるために必要な要件であったからだ。
脳科学者の中野信子さんは、人類が生き延びることができたのは、人類が美を理解することができたからだという。中野さんが例として挙げるのは、ヨルダン南部にあるネアンデルタール人とホモ・サピエンスの2つの遺構である。いずれも海岸から55km離れたところにある。
ホモ・サピエンスは、他のさまざまな旧人類との生存競争を生き抜いた我々現代人の祖先である。他方ネアンデルタール人は、ある時期ホモ・サピエンスと共存していたとされるが絶滅した旧人類である。
2つの遺構の出土品を調べてみると、1つ大きな違いがあった。ホモ・サピエンスの遺構の出土品には、食用とならない小型の貝殻の化石が含まれていたのである。この場所は上述の通り海外から55kmも離れている。日本の貝塚のように食用として採った貝を大量に捨てた場ではないことは明らかであるつまりホモ・サピエンスは貝を食用としてではない、なんらかの目的で入手し、日常で使用していた。推測されるのは、地位や権威を表す象徴として使われたということだという。
一見生活には無関係な貝が、象徴的なものとしてホモ・サピエンスの遺構だけから出土していることは、彼らが目先の物の価値だけでなく、「美しい」という価値を重視していたと考えられると中野さんは述べる。すなわち、ヨルダンの遺構を「美しい」と感じる価値観を持っていた集団が、現在までに生き延びた証明であるのだ。美術品を鑑賞し、美意識を高めるために美術館や画廊を訪ねることは、日常生活から切り離された不要不急の行為だと思われがちだ。しかしながら、美を感じるということは私たちが生きるために不要でも不急でもなく、まさに必要不可欠のことなのだ
■現代アートを理解する脳と苦手な脳がある
美を感じ取る力を鍛えると、脳の活動領域が広がることがわかっている。ロンドン大学のセミール・ゼキ教授は、美術作品を見て「美しい」「これは自分にとって良いものだ」と感じると前頭葉の内側眼窩前頭皮質の血流がアップすることを証明した。血流アップは美術作品だけでなく美しい顔を見たときにも起こる。またそれほどでもないと思うような人でも、その人の笑顔を見ると、この領域が反応する。
かくのごとく、アート思考、美に対する理解は現代ビジネスにおいて大きなファクターとなりつつある。
だが、アートはともすると「美しい」という観点からはずれるような場合もある。とくに「現代アート」は、その発展と分化が激しいため、美しさを感じとることは難しい。美しいどころか嫌悪を感じる人もいるだろう。
印象派のモネやルノワールの美は理解できるが、キュビスムのパブロ・ピカソやフォービズムのアンリ・マチス、ワシリー・カンディンスキーの抽象画を初めて観てから、「美しい」と感嘆するまでには時間がかかりそうだ。しかしながら中野さんは、そういった作品を見ながら「なぜいいのか」を考えることは脳の活動領域を広げることになると話す。よってアート思考は、ビジネスにおいては停滞しているものごとを活性化させ、拡張させるには極めて有効なのである。
とはいえ誰もがアート思考の技術を身に付けられるとは限らない。
中野さんによれば、印象派以降の現代アートについては、わかる人とそうではない人がいるらしいという。もちろん美しいものを美しいと感じるかどうかはまったく個人の感性の問題である。ただ現代アートに限らず、アートを解釈し、理解するためには一定の美のセンスがいるし、センスを磨くためには数多くの美術作品にふれる必要がある。
■コミュニケーションは言語より視覚情報のほうが伝わる
アートを日常や仕事に活かそうとすれば、やはりある程度の基準やレベルが求められる。組織や集団に理解してもらうためには、ある程度、共通のわかりやすい美がそこに存在しなくてはならないと考えられる。
そこで参考にしたいのが、組織開発人材育成パートナーの肩書を持つ三宅未穂子さんが提唱する「絵本によるマネジメント」である。
アート思考がなぜビジネスの世界でこれほど注目されているのかは、上述したとおりであるが、加えて言えば、そもそも人間が受け取る情報のなかでは、見て受け取る情報が最も多いからである。
コミュニケーションの基本は言語だと言われているが、カリフォルニア大学の言語学者アルバート・メラビアン教授が説いたように、コミュニケーションを取る際の影響の比率は、視覚情報が55%、聴覚情報が38%で、言語情報は全体の7%に過ぎない。
視覚に訴える絵本が、ものごとを伝える媒体として最適なのは理解できるだろう。
■絵本を読み解くことで、その組織の課題がわかり、解決策が見い出せる
だがマネジメントを絵本で学べるものだろうか。そもそも企業に勤めている人すべてがマネジメントを学ぶ必要があるのだろうか。マネジメントは役員以上の経営層、あるいはそこに向かって仕事をバリバリする上昇志向の強い人が必要とされる知識・技能なのではないか。自分は関係ないと思う人もいるだろう。
しかし現代の組織においては、マネジメントの知識や手法は組織のあらゆる階層において必要とされる知識・ノウハウである。マネジメントについては数多の学者、経営者が論を語っているが、三宅さんは、「(職場や組織を)よりよくするために、なんとかかんとかすること」と定義している。だが、多くの組織や職場では “よりよくしようと、なんとかかんとかする”ものの、思い通りにならないことが多い。三宅さんはそれは「伝わらなさ」で起こっていると話す。
そしてこの「伝わらなさ」を追求し、たどり着いたのが「絵本によるマネジメント」なのである。三宅さんは絵本を通じたマネジメントの浸透による組織改革を18年にわたって行ってきた。
なぜ絵本なのかという問いに三宅さんは、1つ目に絵本のサイズが大きくも小さくもなく、職場にベストサイズであること。2つ目として、テキストとして短くわかりやすいことを挙げる。つまり時間に追われる職場にはぴったりだということだ。
三宅さんは様々な人材開発の現場で、絵本を使ったマネジメントを浸透させることで、組織のコミュニケーションはもとより、組織そのものが変わっていたことを実感している。たとえば次のようなことだ。
「残業が減った」
「現場自ら時間管理ができるようになった」
「業界の品質力を競うコンテストで1位になった」
「実は、リーダーとしての力があったことが、誰の目にも見えるようになった」
「パートさんから業務改善の声が増えてきた」
「現場力が上がり、管理職の仕事も変化した」
「伝えていることを的確に捉えてくれるようになった」
「一歩先の仕事を準備するようになった」
「人間関係のトラブルがなくなった」
「サービスの対応が良くなったとお客様に褒められた」
「お客様が増えた」
「チームが明るくなった」
「これまでどこか他人事だった人が責任を持ってやってくれるようになった」
など。
もちろん組織によって課題はさまざまある。そこでこうした結果を生み出すために、三宅さんは企業の課題に合わせて設定テーマを次のような9つの項目に体系立てている。
①理念を読み解く(理念教育)
②人間関係力向上(コミュニケーション力)
③商品サービス力向上(ホスピタリティ力)
④チーム力を強くする(チームワーク力)
⑤自己成長(社会人基礎教育)
⑥チーム力で変化を起こす(イノベーション)
⑦誰もが輝く職場づくり(人間力向上)
⑧リーダー力・マネージャー力(リーダーシップ)
⑨幸せな生き方を目指す(感謝力)
三宅さんはこれらのテーマに沿った絵本を100冊用意しており、さらに現場の声に沿った24️冊に絞って、各組織が自走できるプログラムをつくっている。

■人材不足が恒常化している今、取り入れたい絵本を使ったマネジメント研修
三宅さんが現代の組織においてもっとも重要な課題として挙げるのが、人材の問題だ。いうまでもなく現在日本は空前の人材・人手不足であり、企業の成長性・継続性を阻んでいる。
漏れてくるのは、「人が育たない」「次世代のリーダーがいない」「各部署の連携がうまくいかない」「部署内の士気が低い」「人材教育に手が回らない」「離職率が高い」「雇用が安定しない」「慢性的に人手不足を感じている」「全員が日々の業務に追われている」といった言葉だ。
それらの多くの悩みについて、三宅さんは「その背景には、次のようなことが起こっている」と指摘する。
①1人に何役もの仕事が課されるのが当たり前化している職場
②ご機嫌伺い(上長が離職を恐れて、いうべきことを言わない。仕事が集中している人に過剰に配慮する)が習慣になっている職場
③透明人間(見ても見ぬふり、余計な意見は言わない)が多い職場
④「ここだけの話」が生まれる(会議やミーティングで意見が出てこないが、会議を離れるとここだけの話の意見が出てくる)モヤモヤの空気に包まれる職場
⑤「どうせ」(―言っても変わらない。やっても評価されない)の空気が流れる関係性
⑥深く考えないこと(誰かが起こしたミスに別の誰かが蓋をして見えなくするなど)をチョイスしてしまう職場
⑦「ありがとう」(いつの間にか整っている。準備がされているなど、やってもらっていることが当たり前になっていることに対する感謝)不足の組織
⑧てんでんバラバラ(見たい景色、あるべき姿があるものの、各自の取り組みがバラバラ)な組織の現場
⑨電波障害(情報発信者と受信者の齟齬)が起こりやすい現場
つまり、今になって急に人の問題が出てきたのではなく、以前から問題がくすぶっていたと言えるのだ。こうした慢性的課題について三宅さんは、絵本を使った課題点の抽出と「自分ごと化」の浸透で、薄紙をはがすように解決に導いてきた。
■ロシアの絵本『おおきなかぶ』が変えた社歴60年の企業風土
たとえば、60年の歴史を持つある商社では、絵本を使ったマネジメント研修によってバラバラとなっていた社員の心が理念に向かってまとまり、社員一人ひとりが会社全体の課題を「我がこと」として取り組むようになった。
その会社は韓国との食品貿易を業務としており、現在の女性社長の祖父母が、日本において韓国への理解が乏しかった時代に創業。その後2代目が飛躍的に業績を伸ばしたものの急逝。そしてまだ若い彼女が会社を継承した。目指したのは掲げた理念通りの「私たちみんなで幸せになる会社」。しかし、会社には先代の強いリーダーシップによって動いていた旧い体質があったため、多くの課題を抱えていた。
この会社に提案した絵本が『おおきなかぶ』だった。『おおきなかぶ』は、ロシアの昔話で、文豪のトルストイが改めて書き下ろしたことで知られる。日本では1962年に発行されて以来、日本中の学校の図書館や書店に置かれているロングセラーの代表で、小学校1年生の教科書に長く掲載されていた。
「うんとこしょ、どっこいしょ、まだまだかぶは抜けません」というフレーズに聞き覚えのある人も少なくないだろう。
改めてこの本を企業の社員に読んでもらうと、どんな感想が出てくるだろうか。
三宅さんによれば、大半が「力を合わせることで、大きなかぶを抜くことができた。協力する大切さを知った」というようなチームワークについて語る例が多いという。
もっともな答えだが、なかには「そもそもどうしてこんなに大きくなるまで放っておいたんだ。事前に手を打つべきではないか」といった意見も出てくるという。こうした発言をする人は、大概がリスクマネジメントを担う財務担当者や管理職だそうだ。
また「仕事に取り組む姿勢がいかに大切かを教えてくれる」といったような感想も出てきたというが、「仕事のふりをしてる人が多い」といった指摘をする人もいる。
さらにひねくれた見方も出てきた。「よく猫の誘いにネズミが応じたな」とか、「猫はどんな掌握術を使ったのか。取引の条件は何だったのか。それとも脅威のパワーによって、あるいは敵対しても共通の問題で手を組んだのか」など、様々な推測が生まれ、そこからさらに推測が生まれていった。
ほかにも、「なぜおじいさんは自分よりもっと力のある人を呼ばなかったのだろうか」「そもそもネズミが参加するくらいで抜けるなら、他の人たちがもうちょっと頑張ればよかったのではないか」といった感想を持つ人たちもいた。
つまり「おおきなかぶ」を、組織に属する社会人が読むと、そこから出てくる感想はその職場にある課題に対してのものとなっていたのだった。

■絵本にある物語の空間を埋める人や環境から表情や感情を読み解く
三宅さんによれば、絵本の巧みなところは、物語の空間を埋める人や環境に表情や感情があるところだという。
この作品では、おおきなかぶがなかなか抜けないため、1人、また1人と応援を呼びに行くものの、その間の待ちの姿勢は半分諦めムードで描かれている。すっかりやる気をなくしているようにも見える。そこには戦略を立て直そうという気概は見えない。だが1度だけ最後に猫がネズミを呼びに行ってきた時だけ、かぶの周囲に集まってみんなで考えている。
やっと全員が「このままではダメだ。ちゃんと戦略を立てよう」と思ったのだろうか。この絵本では「誰かが加勢を呼びに行った。もうこれで安心」という依存型では結果が残せない。チームで何度も話し合って、もっと良い手段を見出す。それぞれの力を最大に引き出すことが必要だとここから学べるはずだ。
ときには共通の目的のために、気の合わない人やライバルとも手を組むという「オトナ」の知恵も求められる。おおきなかぶは、そのことを見事に描いている。
猫に呼ばれたネズミは、日頃の敵である猫の要請に応えるが、決して心を許して参加しているわけではない。ネズミは猫を引っ張るが、いつでも逃げ出せるように尻尾だけを絡ませている。たったそれだけのことで抜けたのなら、ネズミは要らなかったと捉えられてもいいだろう。
だが結果としてネズミの力は必要だった。
三宅さんは多くの企業に呼ばれて研修を行っているが、4月には企業に入る新人研修に必ずこの大きなかぶの話を取り入れるという。そしてこう呼びかける。
「新入社員の特権は、その存在の力です。あなたという人が真剣に仕事に向き合おうとしているその姿勢であり、その気概がみんなの元気を引き出します。だから挨拶、返事、笑顔。これだけは誰にも負けないような気持ちで取り組んでみましょう」と。
新人の力は、おおきなかぶでいうところのネズミの力。大したことはないと思われていたが、みんなのやる気が引き出され、抜けなかったかぶを抜くことができた。その存在の力で何十人もの気持ちを動かすことができるのである。さらにこの「小さな力」とは存在の価値を表すだけでなく、仕事のひと手間、小さな気づきによって生まれる差を意味する。
三宅さんが絵本を通じたマネジメント研修でとくにこだわって伝える「微差」の力だ。
■生産性の阻害要因は何かを学ぶカナダの『せかせかビーバーさん』
人材不足が常態化している企業においては、仕事の生産性を高めることが強く求められている。
三宅さんが生産性を高めるマネジメントを学ぶ絵本として提供するのが、2012年に発行されたカナダの絵本、ニコラス・オールドランドが描いた『せかせかビーバーさん』。
『せかせかビーバーさん』は、いつもせかせかして行き当たりばったりのビーバーの物語。主人公のビーバーさんは、1分1秒も無駄にできないと、せかせかと仕事をするが、せかせかし過ぎて、人に迷惑をかけていることもわからないほど。ある日とうとう怪我をして入院する羽目になる。ビーバーさんは動けなくなったことで、自分がいかにあれもこれも中途半端だったことを思い知らされる。そして今までみんなに迷惑をかけたことを反省し、改心し仕事のやり方を見直すという話だ。
まさに時間や情報に溺れる現代人の姿をビーバーが代弁している絵本となっている。
この本の優れているところは、せかせかし過ぎて怪我をして入院するが、ベッドの上で今までやってきたことを振り返り、中途半端であったことに気づくビーバーさんの姿である。そして最後まできちんとやり遂げなければと決心し、トレーニングを自分に課すところにある。
まず置かれた状況を把握し、そしてこれまで失ってきた信頼の回復を優先する。ビーバーさんは、まわりに対してどんな謝り方がいいのか、謝罪の練習もしている。そして仕事を段取りよく進めていくことを覚え、実践する。その結果ビーバーさんは自分の目標をやり遂げている。
失敗を振り返り、自らの過ちを認め、その改善策を考えるという筋立ては、きわめて寓意性に富むが、その対処法を細かくみていくと、実は当たり前だと思っていたことや、同じ言葉を使っているのに受け取り方のずれが誤解を招き、誤解を解こうと動いても「せかせか」しているために、却って問題を大きくしてしまう様子が見えてくる。
そこで三宅さんはこの『せかせかビーバーさん』を使った研修で、職場に必要な共通言語について語るという。

■PDCAは組織の誰もが理解している共通言語なのか
ビジネスにおいては、何か問題がありそうなときはまず現状を把握し、原因や要因を分析して問題を解決するための計画を練り、それを実行し、その結果をまた分析し、改善策を考え、実施することを繰り返す。いわゆるPDCAである。
しかしながらこのPDCAという言葉は、あらゆる職場に浸透しているとは言い難い。PDCAの正しい方法や、そのための準備、計画の立て方、あるいは報告書の書き方など、そのやり方やルールが、かかわる全員のなかで共通言語化されていないと、PDCAは十分に機能しない。
共通言語が浸透していたとしても、その意識が「自分の仕事だけすればいい」という理解と、「全体の中で自分が果たす役割」を理解して取り組む場合では、生み出されるアウトプットが大きく違うはずである。
三宅さんは、せかせかビーバーさんを通じて、当たり前化しているPDCAサイクルを見直し、そこから発展させていく仕事のPDCAループは、一人ひとりが持っていることに気づくべきと説く。
一人ひとりのループを理解していないために起こる支障を、三宅さんはたくさん見てきたという。
“それぞれの仕事量や内容を知らず”に、自分の部署の仕事を他部署に割り込ませて、他部署の時間を奪っていることはないか。そういう点を学びあい、そこも含めて共通言語にしてほしいという。
そうすると、責任とは何かという問いや、あるいは全体の関係性の中で重複していることを廃棄する勇気を持つことの重要性にも気づいていくと話す。
絵本では、せかせかビーバーさんのおかげで自分の時間を奪われてしまった動物たちがたくさん出てくる。他人を予定外の作業に巻き込むことが、組織の仕事の生産性を止める、もっともしてはいけないことだと気づいてほしいと三宅さんは訴える。
一人の仕事が全体を作るということであれば、自分のPDCAを見直しそのサイクルタイムもしっかり見直す。一人ひとりが目指している仕事のサイクルを共有し、その認識の違いに気づき生産性を追体験する。せかせかビーバーさんはこのプロセスが有効に働くように促してくれる絵本だと三宅さんはいうのである。
■「見える化」について考えさせるドイツの絵本『たのしいおかたづけ』
マネジメントの世界ではよく「見える化」という言葉が使われる。この「見える化」を理解するために参考になるのが2015年発行の『たのしいおかたづけ』という、ドイツのウルスス・ウェールリが編んだ写真絵本だ。
この本では左ページに対象物のもとの姿、右ページに分解された後の姿の写真がある。
たとえばモミの木の枝は枝と葉っぱに、広場で遊ぶ人たちも、使っていた道具と服を色別に並べられている。同じようにクリスマスツリーも夜空の星も分解されている。分解の基準は色や形、サイズなどさまざまあり、意表を突いた分類法もあって、大人も十分楽しめる内容となっている。
三宅さんは、この絵本は職場の業務改善の基本を教えてくれると話す。業務の改善には、物事を構成しているものは何かが見えなくてはならない。しかし、そこを知るのは手間も時間もかかる。“せかせかビーバーさん”が多い組織であればなおさらである。
なんとかかんとかしてより良くするための改善案を作る前に、生活の中にある「変えたいけど変わらないこと」、「ぐずぐずしていつも後回しにしている大切なこと」、「ぐちゃぐちゃとなっている引き出し」、「いつ見てもわからない書類の山」、「いつも遅れる提出物」「どこかで滞ってしまう情報」といったものを一度全部集めて並べて見る必要があると三宅さんは述べる。
「そうすると何がそこに存在しているのか、何が必要で何が要らないのか、プランが見えてくる」という。また組織において見えないものを見えるようにするためには、何がどこに、どれだけ、どのように存在しているかを「見える化」する必要がある。そのためには分解するだけでなく、「並べる」「組み替える」ことが重要になってくる。
つまり「見える化」するということは、分解するということ、分解したものを何が必要で何が要らないのかをさまざまな分類方法によって並べ替えてみる、組み替えてみるということなのである。
工場などの現場では、整理、整頓、清掃、清潔、躾といったいわゆる5Sの取り組みがなされているが、こうした取り組みはルーティン化し過ぎたことで、何を目的にやっているのか見失ったり、当たり前化しすぎて、改善や改革につなげにくい状態になっている可能性もある。当たり前化して充分効率化されているという過信をあらためて問い直す意味でも、この『たのしいおかたづけ』は参考になる絵本だと言える。
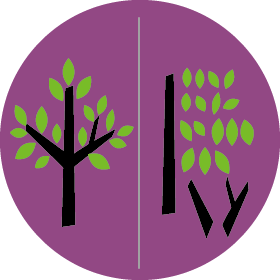
■イノベーションのきっかけを与えるアメリカの『ながーい5ふん みじかい5ふん』
ビジネスの世界では、イノベーションという言葉も頻出する。経済紙では載らない日がないほどだ。このイノベーションを起こすために力を与える絵本がある。
それが2019年発行のアメリカの絵本『ながーい5ふん みじかい5ふん』。文と絵が別々で文がリズ・ガートン・スキャロンとオードリー・ヴァーニック。そして絵がオリビア・タレックで訳が木坂涼。
この絵本の主役は幼稚園年長ぐらいの男の子で、彼が感じる5分と大人の5分の違いをさまざまなシーンを通じて一緒に体験させてくれる。例えば歯医者さんの待合室の5分はあっという間なのに、歯を削られる5分はとても長いなど、5分間という間に起こる身近なエピソードを通じて、時間の不思議さや面白さに触れることができる。とくに主人公の男の子の表情から5分という時間が長いのか短いのか、どういう時間的な意味をもつのかが考察できるところがこの絵本の秀逸なところだ。
現代社会では一日が24時間で刻まれ、1分、1時間は誰にとっても1分、1時間だ。しかしこの絵本の作者が描いているように、大人の5分と子どもの5分の感じ方は大きく違う。あるいは大人でもその状況によって同じ時間を長く感じたり短く感じたりする。
アインシュタインの相対性理論を出すまでもなく、時間はそれを使う人によって感じ方が変わる相対的なもの。これは例えばレストランの注文を考えてみると理解できるだろう。
注文した料理が運ばれてくるまでの時間が5分だとすると、その時間は長いだろうか短いだろうか。場所が高級レストランとファミリーレストランでは、どうだろう。昼時と夕方ではどうだろう。注文者が仕事に追われるビジネスパーソンならどうか。大人数のグループならどうか。定年後の比較的時間のある高齢者ならどうか。
あるいはレストラン側に視点を転じると、その日その時間は混雑しているため一人ひとりのお客様の対応を必死にやってるけど追いつかず、これで精一杯という時間が5分なのかもしれない。同じ時間を過ごしているのに、お客様が感じている時間とサービス提供者の感じる時間は等しくないということが容易に想像できる。
私にとっての当たり前が、彼にとっての当たり前じゃないという新しい発見につながったりする。さらに三宅さんは、この5分を「もう」と捉えるか、「まだ」と捉えるかで大きく未来の可能性が変わるとする。つまりこの捉え方こそがイノベーションの機会となるというのだ。
考えに考え抜いた結果生まれるイノベーションや発明は、みんなが願うところかもしれない。だがむしろ物事の捉え方を少し変えてみる、視点を少しずらしてみるということが、イノベーションのきっかけになる。この絵本はその視点を与えてくれる。
■個性の引き出し方とリーダーシップを学ぶアメリカの『スイミー』
人材不足の昨今では、組織に属する人の能力開発が盛んだ。人が持つ個性や能力をどう引き出し、活かしていくか。その参考になる絵本の1つが、1969年に発行されたアメリカの『スイミー』という作品。スイミーは日本の小学校の教科書にも載っていたことがある有名な作品なので、読んだ人も多いのではないだろうか。
作者のレオ・レオニの独特の画風が潮の流れや光のゆらぎまでを見事に表している美しい絵本で、訳者が日本を代表する詩人、谷川俊太郎であることも話題となった。
主人公のスイミーは、赤い小さな魚の兄弟の中で一匹だけ真っ黒。ある日魚がやって来て一匹残らず飲み込んでしまった。残ったのは泳ぎの速かったスイミーだけ。ただ一匹になった小さなスイミーは広い海でさまざまな生き物と出会い、海の世界を体験する。
三宅さんによれば、この本はスイミーが様々な出会いと学びの中から強いリーダーシップと優れたマネジメント方法を学んでいく物語だという。広い外敵の多い海の中で、小さな魚たちが、どのように生き延びていくかをスイミーはリーダーシップを発揮しながらまとめていく。スイミーは小さな魚たちが一緒になって泳ぐことで、大きな一つの魚のふりができ、天敵から自らを守っていけることを教え、スイミー自身は自分の体の黒色を生かして大きな魚の目となって一緒に大海を泳ぐのだった。
どこかディズニーの『ファインディング・ニモ』にも通じるような話だが、ニモと違う点は、スイミー自身がほかの仲間と違う黒色をしていたということだ。自分だけ仲間はずれの色だったことをスイミー自身は嫌っていた。仲間と違うことで一人ぼっちの孤独感や寂しさも知っており、知っているからこ
そ仲間との団結の重要性を強力に伝えたと思われると、三宅さんはいう。
三宅さんはこの物語の中で特にスイミーの2つの言葉に注目している。
「みんな一緒に泳ぐんだ。海でいちばん大きな魚のフリをして」
「 スイミーは教えた。決して離れ離れにならないこと。みんな持ち場を守ること」
スイミーは自分を認めることで、「そうだ!一緒に泳ぐんだ」と仲間をまとめる力を発揮でき、ただ鼓舞するだけでなく、「みんな持ち場を守ること」と全体をマネジメントした。
「持ち場を守る」ことは持ち場に対しての責任を持つということでもある。
三宅さんはこの作品の「自分一人ひとりが現場をマネジメントする一員である」ことをスイミーが導いているところに感動しているという。
さらにスイミーの強みが後天的に習得したものではなく、本来持っている、他の人が気づかないその人の魅力、能力であることを三宅さんは重視している。
自分で自分を評価するのはなかなか難しいものだ。自分が「嫌だ」「嫌いだ」と思ってきたことが実はほかの人にとって魅力であったり、ほかの人のためになる優れた力であったりする。
三宅さんはスイミーを読んだ後に、自分では気づきにくい強みをお互いに教え合ってみることもとても有効ではないかと語っている。
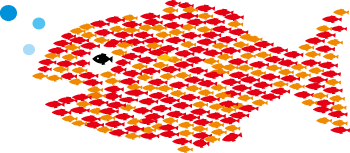
いかがだろうか。絵本には脳を刺激する美しいビジュアルと、実にさまざまな宝のような示唆が埋め込まれている。社会人として経験を積んだ今だからこそ。あるいは、社会人として未熟を感じた今だからこそ見つけられる宝がある。ぜひ機会があれば、絵本から自分の宝を見つけてほしいと思う。
参考
【書籍】●『絵本はマネジメントの教科書』三宅未穂子〈みらい〉 ●『大学4年間の西洋美術史が10 時間で学べる』池上英洋〈KADOKAWA〉●『西洋美術史年表』池上英洋・青野尚子〈新星出版社〉 ●『非言語コミュニケーション』マジョリー・F・ヴァーガス/石丸正:訳〈新潮選書〉ほか
【参考サイト】● Vogue Japan ●六本木アートカレッジ ●現代ビジネス ●京都新聞 ●文藝春秋 電子版(動画)●福武教育文化振興財団設立35 周年記念講演(動画) ほか
POINT
■ ホモ・サピエンスが生き残れたのは、美を理解していたから
■ 美を感じ取る力を鍛えると、脳の活動領域が広がる
■ 現代アートを理解する脳と、苦手な脳がある
■ コミュニケーションは言語より視覚情報のほうが伝わる
■ 絵本を読み解くことでその組織の課題がわかり、解決策が見出せる
■ 人材不足が恒常化している今こそ絵本を使ったマネジメント研修を取り入れる
■ 絵本は絵のわかりやすさ、サイズ、文章の長さが最適
■『おおきなかぶ』で小さな力の大きな影響を考える
■『おおきなかぶ』を抜くにはなぜそんな人数と動物が要ったのかを考える
■ 絵本にある、物語の空間を埋める人や環境から表情や感情を読み解く
■ 生産性の阻害要因は誰かの仕事を止めること
■ PDCAは組織の共通言語であるとは限らない
■ 一人ひとりの仕事のループを確認する
■「見える化」には分解だけでなく、「並べる」「組み換える」ことが重要
■ ある状況の5分を「もう」と捉えるか、「まだ」と捉えるかで未来が変わる
■ 後天的ではなく、もって生まれた個性を引きだし活かす
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム