全てのビジネスパーソン必読!AI時代に求められる「気づき力」を鍛えよ! 1
ビジネスの現場では、目に見える成果が評価される。しかし、その成否を分けているのは、目に見えない「気づき」であることが少なくない。顧客の一言、現場の小さな違和感、チームメンバーの沈黙。そうした微細なサインを察知し、意味づけをして、行動につなげられる人が力を発揮する。いま、あらゆる業種とキャリア層にとって「気づき力」は必須のビジネススキルとなっている。ビジネスにおける気づき力とは何か。その本質から鍛え方、現場での活かし方までを考察してみる。
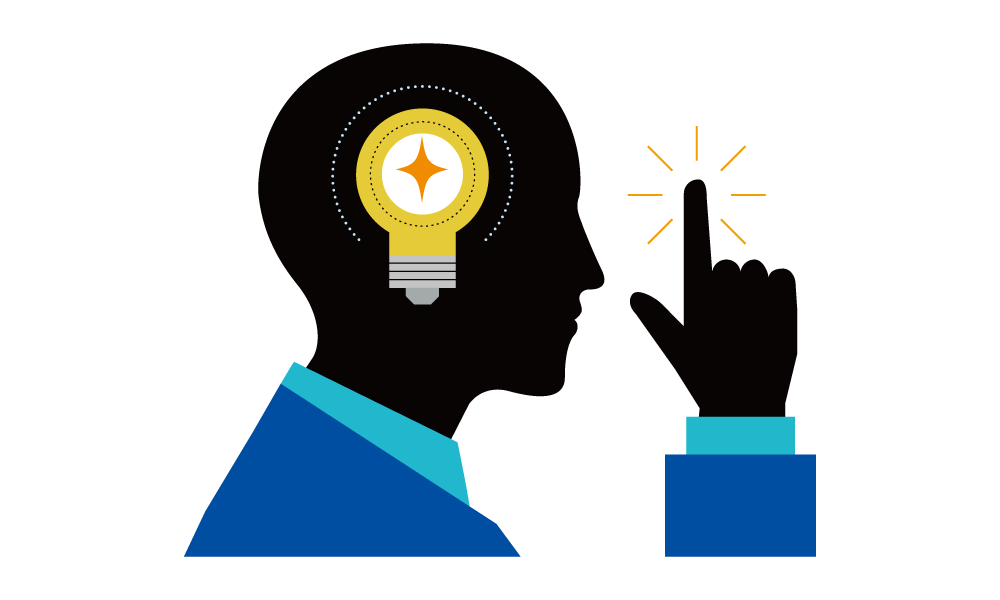
目次
■なぜいま「気づき力」が必要なのか
「もっと早く気づいていれば─」。
ビジネスの現場では、そんな言葉がしばしば聞かれる。売上の急減、顧客の離反、現場の疲弊、人材の流出─。こうした“現象”は、突然起きたように見えて、実際にはその前に小さな“サイン”が出ていることが多い。
ただそれに気づけなかった。あるいは、気づいても深く捉えずに流してしまった。その結果対応が遅れ、事態が深刻化する。そんなケースはあらゆる業種で繰り返されている。
いまビジネスにおいて「気づき力」がかつてないほど重要視されている。背景にあるのは、社会や市場、働き方そのものの劇的な変化だ。テクノロジーの進化でAIや自動化が進み、ビジネスパーソンに求められるスキルの中身が大きく変わってきている。かつては「速く正確に処理する力」が評価されていたが、いまや仕事の多くはロボットやAIに代替される時代となった。いま人類は、「人間にしかできないこと」を問い出したと言える。その代表が「気づくこと」である。
では気づくための「気づき力」とは何だろうか。
「気づき力」に近い言葉に「観察力」や「洞察力」、「注意力」、「分析力」などがある。
注意力は、多くの情報から特定の事がらや情報に集中する能力を指し、「注意散漫」など、最も日常的に使われる心理効果を生む能力の1つだ。
また観察力とは、周囲の状況や事象を注意深く観察して変化や違いに気づく能力で、五感を駆使して情報を収集し、物事の状況を客観的に捉える力を表し、ビジネスパーソンのみならず、およその専門家、課題や研究に向かう学生にとっても不可欠の能力とされる。
洞察力もビジネスパーソンには不可欠の能力で、よく観察力と対で登場する。観察力は目に見える、注意深く聴く、匂い、手触りなどからわかる変異や違和感を感じとる力で、対して洞察力はそういった違和感や変異から本質を問う。推測や仮定の問いを繰り返しながら、物事の本質や起こったことの真因に迫る能力のことだ。
また分析力も重要で、まさにDX時代においてさまざまな予測や計画を立てるうえでは不可欠の能力とされる。
いずれも“できる”ビジネスパーソンに不可欠の能力とノウハウだが、気づき力はそれらを含みつつも、より総合的で実践知に近い性質を持つ。単なる「目の良さ」や「分析力の高さ」ではなく、日々の業務や会話、データや現場など、目の前の情報や空気感からまだ言葉になっていない兆しや違和感をすくい上げ、それを意味づけして活かす力のことである。つまりビジネスパーソンに求められる「気づき力」とは、「気づいて終わり」ではなく、「気づいて活かす」実践力なのである。
■髙田明さん、矢野博丈さん、宗次徳二さん。優れたリーダーは「気づき力」が高い
実際大企業を築きあげた創業者や経営者には、優れた「気づき力」の持ち主が多い。
独特の声で家電のテレビ通販市場を広げた、「ジャパネットたかた」の髙田明さん。創業時は大量のチラシを撒いて、家電やカメラの販売を展開していたが、さっぱり売れなかった。ある時、ラジオやテレビで語りかけると売れ出した。それまでは製品の機能や価格を訴求してきたが、製品を使った生活シーンを熱く語るようにしたのだ。とくに当時の主力だったカメラやビデオカメラはさまざまな機能がついており、製品の機能をすべて訴求することは難しかった。だから髙田さんは、そのカメラを持つことによって作り出される家族の物語が求める価値であることに「気づいた」のだった。
また「100均」の言葉を生み出した「ダイソー」の創業者、矢野博丈さんは、雑貨品の移動販売をして全国を渡り歩いていた頃、ある主婦に「これ100円にしてくれたら買うわ」と言われ、すべての商品を100円均一にした。矢野さんは、当時、商品の価格を毎回仕入れ価格と売れ筋などを考えて1円単位でつけていたが、その作業がとても手間だと考えていた。矢野さんは「お客は100円で買う理由を考えている」と気づき、「いっそ100円均一にしよう」と思ったのだ。すべて100円なので売れ残っても値下げする必要はなく、別の場所で売ればいいだけ。仕入れの価格交渉もしやすくなり、不思議なことに返品も激減したという。
“ココイチ”の愛称で知られる「CoCo 壱番屋」の創業者の宗次徳二さんは、1軒の喫茶店から日本でもっとも知名度のあるカレーチェーンを築いた立志伝中の人だ。現在はココイチをハウス食品に譲渡し、NPO法人の代表としてクラシック音楽の普及をはじめとした社会貢献に取り組んでいる。そのココイチを成長させた原動力がお客様からのアンケートはがき。いまでも各店舗に置いてあり、気になったことや感じたことがあれば、はがきに書いてポストから投函する仕組みとなっているが、宗次さんはこのはがきを読むことを一番の楽しみにしていた。店舗だけでキャッチできないクレームをしっかり聞き、対応していくことで、とくにカレーの中身以上に接客レベルを上げることが重要だと気づいた。実ははがき以上に重視したのが各店舗回りだった。宗次さんは飲食店経営者の会合などには顔を出さず、ひたすら店舗を回って、お客さんの様子を観ていた。とくに店を出て行く際の姿をチェックし、満足して出たか、そうでないかを判断していた。「満足した人は足取りが軽快だが、満足しなかった人は、無言で早足」という気づきを得ていたからだ。
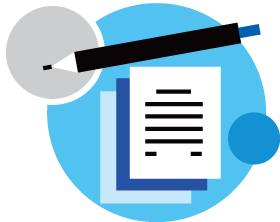
■量販店での気づきから「なるほど家電」戦略を打ち出した大山健太郎さん
いまや家電の総合メーカーの一角となった「アイリスオーヤマ」。もともとはプラスチック容器の製造メーカーだったが、「アイリス」ブランドの園芸用プランターをヒットさせて成長、そこからペット用品、オフィス用品、家具、インテリア、キッチン用品、ヘルスケア製品などアイテムを着々と拡大していった。それでも創業者の大山健太郎さんは、大メーカーひしめく白物家電市場に参入する際は、慎重に市場動向を見極めた。大山さんは量販店で買い物をする高齢者の姿を観察し、高齢者にとっては「文字が小さくて読みづらい」ことや「リモコンが複雑で扱いにくい」こと、「製品が多機能すぎる」、「デザインより使いやすさを求めていること」に気づき、「なるほど家電」と銘打ち、誰でも使えるシンプル家電の開発を進めたのだった。
ユニクロブランドを展開する「ファーストリテイリング」。世界に冠たる巨大アパレルメーカーを率いる創業者の柳井正さんも、創業間もない頃に経験した失敗が成長の気づきとなっている。柳井さんはユニクロ2号店で大きな失敗をしたが、そこで気づいたことは「立地の重要性」だった。まだインターネットが発達していなかった時代。柳井さんはいかに商品がよくても立地が悪ければ、消費者に届かないということがわかったのだ。その後も柳井さんは失敗を重ねている。その自伝のタイトルにもなっているように、現在の成功の秘訣は「1勝9敗」。つまり何度も失敗し、そこからさまざまな気づきを得て、成長の糧にしていることである。
■夏にあたたかいおでんを売り出した、セブン-イレブンの鈴木敏文さん
数多の有名経営者のなかでも「気づきの天才」と呼ぶべき人物が、日本にコンビニエンスストアという小売形態を持ち込み、そこから世界中に広げたセブン-イレブンの創業者、鈴木敏文さんだろう。鈴木さんは、在庫切れが予測される商品を、レジを通すだけで自動で発注するPOSを導入したりなど、現在のDXに先駆け、日本の小売流通システムに革命を起こした人でもある。鈴木さんの気づきの素晴らしさは、データと現実の現象を常に照らし合わせて、解析するところにあった。鈴木さんは気温変化が激しくなる春先や秋口に意外な商品が売れることに気づいた。夏場でも気温が25℃を下回ると冬の定番である温かいおでんが売れだし、逆に冬場でも25℃以上となると半袖シャツが売れだす。また春先に前日より気温が上がると、夏に売れる冷やし中華が売れだすなどの法則を見出している。こうしたデータは分母と分子の差で見るべきで、分母が夏であれば、25℃は寒い。分子が冬で25℃であれば、暑いと感じる。この考えを「統計心理学」と称して、セブン-イレブンの仕入れに反映させている。
自動車の排ガス分析機器で世界シェア8割を占める、世界有数の計測機器メーカー「堀場製作所」。創業者の堀場雅夫さんは、創業初期、順調に売上が伸びていたものの、社員があまり楽しそうな表情をしていなかったことに違和感を感じる。堀場さんはせっかく自分でモノを開発できる会社をつくったのに、社員が自由な開発ができていないと気づき、社是を「おもしろおかしく働く」に直したのだった。その後のユニークな経営と飛躍は知られるところ。1997年には「21世紀最強の企業として発展し続ける」ことを目指して「ブラックジャックプロジェクト」を開始。開始から25年以上となる現在もグローバルで展開されており、同社の企業文化の1つになっている。
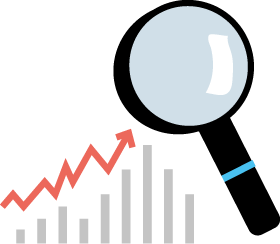
■仕事の基本は「気づくこと」。でないとただのワーカーになる
企業を大きく成長させる気づき力は、こうした“特別な人たち”にだけ備わっているものではない。すべての人が本来持っている力だ。問題はその存在に気づかないまま働き、暮らしている人が多いことだ。
長年化学メーカーに勤務し、技術士の資格を持つ技術コンサルタントの田中進さんはその著書、『「気づき力」が組織を変える、仕事を変える─業務品質を高め成功要因を生みだすためのヒント』の中で、そもそも「仕事は小さなこと、些細なことに気づくことから始まる」と語っている。「気づいて、感じて、察することができなければ何事も始まりません。気づき力が弱いと何も考えず、単に真面目に汗を流して『働く』だけのワーカーとなってしまいます。自分で気づき、感じ、察して、その中からいろんな課題を見出さないと『仕事』をすることになりません」(同書)
■サステナブルに成長をつづける企業には「気づき」を涵養する仕組みがある
気づきはあらゆる仕事の出発点であり、DXやAIの進化にかかわらず、仕事をして何らかの報酬をもらう人であれば、身につけておかなければならない必須スキルなのだ。
このため企業の中には独自の気づき力涵養システムを取り入れているところもある。
有名どころでは、日本を代表するトヨタ自動車の「カイゼン活動」がある。トヨタのカイゼン活動は、「TPS(トヨタ生産方式)」のベースを成す活動の1つで、そのなかでも「なぜなぜ5回」がよく知られている。「なぜなぜ5回」は、その名の通り、起こった現象に対して「なぜ?」という問いを5回繰り返し、原因の背景にある真因を突き止めていく手法だ。トヨタのカイゼン活動の活動主体となる組織は「QC(品質管理)サークル」と呼ぶもので、現場の工程やライン単位でQCサークルを組織し、毎日メンバーが気づきを報告する。気づきはメンバーで共有された後、その違和感や現象の原因をメンバーが「なぜ?」と問い、それに対してメンバーがその原因と思われる解を出していく。そしてその出た解に対してさらに「なぜ?」と問いを重ねるのである。この際、上司は解がわかっていたとしても発言しない。あくまで自分たちで気づくまで見守るのである。
同じく日本を代表するパナソニックでは、その名も「気づきミーティング」と称する小集団活動を行っている。社員全員が週1回以上「改善気づきシート」に気づいた違和感や問題点を書き込む。優れた気づきについては社内イントラで「称賛共有」している。また部署によってはこの改善気づきシートから上がってきた気づきを毎朝10分程度の時間を割いて共有してる。
また食のグローバル企業である「味の素」では、新商品の開発にあたって技術者と営業、生活者が一緒にテストを行う“気づきの共有会”を催している。「感覚記録カード」を用いて、商品を口にしたときの感覚を素直に書き込んでいくのだ。また商品のアイデア会議では、日常の小さな気づきをメモした「ひらめきシート」を持参して臨むことになっている。
また業務効率化のアプリやソフトを開発する「サイボウズ」では、社員がSlackなどの社内チャットアプリや社内SNSを通じ、気づいたことを即投稿できるシステムがある。投稿された提案は、内容次第で即採用される。いい改善提案に対しては経営陣が「素晴らしい」と称賛する文化があり、社員の「気づき」の掘り起こしを促している。また同社ではいい気づきだけでなく失敗も積極的に報告されている。
日本を代表する化粧品メーカーの「資生堂」では、気づきの基本機能である「感性」を鍛える取り組みが行われている。開発やマーケティング部門の社員に対しては、「人間観察」「におい・肌感の微差」「色調の心理的影響」を実体験で学ばせる“五感観察のワークショップ”を行っているほか、週1回、社員が「身近な感覚の気づき」をテーマに上司と気づきを共有する制度も持っている。
有名無名を問わず、いかに企業が「気づき」を重視しているかがわかる。
■気づき力は誰もが持っている。だが発揮できていない
気づき力で大切なのは、社員が「気づきたい」と意識することだ。そして、毎日の中にある「ちょっとした変化」や「微妙な空気の揺らぎ」を、無視せず拾い上げてみる。それだけで、世界の見え方は変わってくる。気づき力は、後天的に磨くことができる「感性の技術」であり、意識と習慣によって鍛えられるスキルである。
実はこの“気づき”という営みは、脳の特定の機能によって支えられていることがわかっている。代表的なのが「RAS(網様体賦活系)」と呼ばれる神経ネットワークだ。これは、脳幹にあるフィルター機能のようなもので、人が無意識に「いま、自分に必要な情報」を取捨選択する働きを担っている。心理学的には「カクテルパーティー効果」や「カラーパス効果」、「バーダー・マインホフ現象」などと呼ばれる事象がこれにあたる。
カクテルパーティー効果はその名称どおり、「ガヤガヤしたカクテルパーティー会場でも、気になる人の話や自分の名前を聞き取れる」心理効果。またカラーパス効果は、赤や緑など「特定の色を意識して生活するとその色が普段より目に付くようになる」心理効果をいう。バーダー・マインホフ現象は、「ある特定の情報を知った後に、その情報がやたら目に入るようになる現象」を指す。
つまり脳の仕組み的に観ていくと、気づいていないことは「見えていない」のではなく、「脳が必要ないと判断してスルーしている」状態で、裏を返せば、「何に注目するか」を自ら意識的にセットすれば、脳のアンテナが自然とその方向に働き始める。営業なら顧客の感情に、製造なら異音やデータのズレに、サービスなら表情の揺らぎに。目的を明確に持つことで、脳の感度は高まる。

■気づきをブロックする人間心理と環境に着目せよ
だが同時に人間は「気づいているようで気づけない」ことも多い。気づけない背景には、心理的なバイアスや環境要因がある。たとえば「確証バイアス」。心理的バイアスの代表で、自分が正しいと思っている都合のいい情報ばかり集め、異なる兆しを見逃してしまう心理だ。とく最近は情報源をSNSだけに頼っている人が多いが、SNSはプログラムやAIがその人が好む都合の良い情報だけを集めるため、確証バイアスに陥りやすい。
ほかには環境要因としての「同調圧力」や「感情抑圧」の影響がある。
同調圧力は、周囲が何も言わないので、言い出しにくい圧力が醸成される状態。違和感を持っても表に出せず、結果的にその違和感すら無視するようになる。同調圧力はとくに和を重んじる文化を持つ日本人が敏感だとされる。また感情抑圧は、本当は不快なのに「気のせいだ」と押し込めてしまい、サインを読み取る気づきセンサーが鈍っていく状態だ。あるいは忙しさや疲労から脳が“気づき”の余裕を奪われている状態もある。当然同調圧力、感情抑圧に疲れや多忙が重なれば、気づきセンサーの感度はだだ下がり状態になる。
こうなるといくら意識していても、気づくべき変化を脳がスルーしてしまう。ゆえに気づき力を高めるには、自分の思い込みや習慣に気づくことが必要になる。「気づきの前提に気づく」というメタ的な視点が問われてくるわけだが、逆に言えば企業は常に社員の気づき力低下が起こらないよう、ワークライフバランスを考慮した風通しのいい社内環境をつくっていかなければならないのだ。
■気づける人と気づけない人
気づき力が不十分だとどんなことが起こるのか。
「それ、前から気になってたんですけど……」。
何かが起きてから、こうした声が上がる場面は少なくない。実は多くの問題には、「前兆」や「違和感」といった“小さなサイン”が存在している。だが、それを見過ごしたり、気づいていてもうやむやに流してしまったりすることで、事態は深刻化し、後手に回る。
たとえば営業で商談を進めるも、「なんとなく良さそうだけど、決めきれない」といった経験をもったことはないだろうか。
■違和感に気づけず、受注を逃した営業担当者
中堅メーカーの営業担当者の田中さんは、長年取引のある顧客に対して新商品の提案を行っていた。プレゼン資料もよくできており、説明も丁寧だった。しかし、顧客の反応は終始薄く、うなずきも笑顔も少なかった。それでも「表情に出にくいタイプだろう」と判断し、そのまま提案を進めた。
数週間後、その顧客が競合製品に切り替えたことを知った。顧客の決裁担当者に理由を聞くと「スペックの高さよりも、アフターサポートや柔軟性を重視しているのに、こちらのニーズには触れられなかった」という答えが返ってきた。思い当たるフシがあった。実はプレゼンの最中、田中さんが話すたびに顧客の視線が資料から離れ、話題を変えたときにだけ少し反応が返ってきていた。その「違和感」に気づけていれば、別のアプローチもできたはずだったと田中さんは悔やんだ。
仮に気づき力が高い営業パーソンであれば、商談中の顧客の言葉尻の変化、表情のゆらぎ、視線の動きなど、非言語的なサインを見逃さずに拾い、そこから相手の本音や懸念に気づくことができる。その場で質問を重ねたり、提案の角度を変えたりして、相手の信頼と成果を同時に生む。しかし気づけない人は、資料通りに進めることに終始し、結果として「なんとなく良さそうだけど決めきれない」という結末を迎えることも多い。とくに「なんとなく良さそう」「脈はある」と営業担当者が受け取った場合、顧客との接触時間も増え、資料づくりにも時間をかけるだろう。予算規模が大きかったり、新しいプロジェクトであったりすれば、担当者以外の人を巻き込むことになる。それが受注に繋がらないとすれば、会社のダメージは大きく、また担当者のキャリアにも傷がつきかねない。
■サービス業は「気づき力」が収益力、さらには命を左右する
サービス業においては、空気の微妙な変化に気づけるかどうかが業績に直結する。
ある飲食チェーンでは、ある店舗だけ売上がじわじわと落ち始めていた。大きなクレームもなく、衛生管理や料理の品質にも問題はなかったが、口コミサイトの評価が下がり、「雰囲気がよくない」「店員が少し冷たい」といったコメントが増えていた。
本部はそれを個人の主観と見なして対応を先送りしていたが、半年後にはその店舗の売上は前年の70%まで落ち込み、ついに人員整理にまで至った。後に聞き取りを行ったところ、ベテラン店長が異動した直後から、スタッフ間の雰囲気が悪化し、連携がずれていき、ホール担当が頻繁に入れ替わっていたことがわかった。客のちょっとした表情や、常連客の来店頻度の変化といった“静かなサイン”に、誰も気づこうとしなかったことが、決定的な原因だった。
こうした静かな変化はある種の生活習慣病のようなもの。気がついた時には「手遅れ」となることが多い。オーダーミスがちょっと増えた、清掃がちょっと粗くなった、などの規律の乱れや緩み、雰囲気の劣化に気づいたとき、いかに早く修正できるかが、大きなダメージを未然に防ぐことにつながる。

■高度な気づき力が日本の「おもてなし文化」を支える
インバウンドの高まりを受け、日本のサービス業の「おもてなし」が世界中で称賛されている。相手を思いやり、見えない小さな不満を感じとり、先回りをして動く。すなわち高い気づき力が日本のサービス業のおもてなし評価を高めてきた。
それは飲食小売業、ホテル業のみならず、医療、教育の現場でも同様だ。
言葉に出されない要望や不安にどれだけ早く、的確に気づけるかが、リピート率や評価に影響を与える。とくに医療機関や教育現場の気づきは人間の命や人生に直結する。医療機関であればプロフェッショナルとして「気づかなければならない絶対ライン」があり、いかなる緊急事態でも的確にその“センサー”を作動させなければならない。また教育では、教師の気づきが生徒の未来を左右することがある。教師が感じる個別生徒に対する違和感が、学習の躓きや阻害原因を解き明かし、その子の未来を拓くきっかけを与えたり、あるいはいじめやそこから引き起こる自殺、事件を防止することもある。

■「おもてなし」が日本のものづくり品質を支えてきた
日本のおもてなし文化で培われたこうした「気づき力」は、サービス業のみならず製造業でも発揮されている。ときにオーバースペックと呼ばれる日本製品の品質の高さは、製品を購入していただいた顧客へのいわば「おもてなし」の具現化であり、たとえば、総重量数トンクラスの自動車における材料のグラム単位の軽量化、1銭単位の削減は、利益率のみならず、お客様へのおもてなしの追求からも来ている。
トヨタ自動車の生産工場では、「後工程はお客様」というスローガンを掲げ、後工程を担当する人へしっかりした品質の加工品・組立品を渡すことを徹底してきた。このスローガンを意識することで、後工程の担当者に対して細かな配慮ができるようになり、業務が円滑に進み生産性が上がっていったのだ。後工程の人への配慮が高まることは、すなわち気づき意識を高め、気づきのポイントを増やす。結果、微妙な変化や予兆を感じとれるようになり、トラブルや事故を未然に防ぐことにつながり、トラブルが起こってもすぐ対応できるようになるのである。
■DXの進展でシミュレーションが発達、製造業の「気づきセンサー」が劣化
しかしながら、世界に誇る日本の製造業も上流工程では、大量データの収集分析、シミュレーション技術の発達などが、人間の「気づきセンサー」を鈍くさせているようだ。
たとえばコンシューマー向けの製品であれば、使用者のちょっとした不便、口コミに潜む不満、使い方の癖といった細部への気づきが、次の商品開発につながるが、この気づきを活かせない事例が増えつつある。
家電メーカーA社では、人気洗濯機のリニューアル版を発売した。しかし販売初期からSNS上に「ボタンの反応が悪い」「使いにくくなった」といったコメントが目立ち始めた。だが開発チームはそれを“声の大きい一部の意見”として扱い、様子を見ることにした。
結果、売上は目標から3割ダウン。在庫を大量に抱え、ブランド価値の低下を招いた。テスト段階で「ちょっと使いづらいですね」とつぶやいていた数人のモニターの声を、単なる個人の感想として扱ったことが要因だった。とくにコンシューマー向けのヒット商品の場合、新機能搭載によるデザイン変更などはコアな支持層離れが起きやすく、注意が必要だ。
業者向け製品を扱うBtoBの現場でも同様のことが起きている。ある搬送機器メーカーでは、物流現場への納品プロジェクトで失敗した。設計段階で現場視察に入った際、担当者が「ここ、通路が結構狭いんですよ」と何気なく放った言葉を“雑談”として処理し、仕様変更のポイントとして反映されなかったのだ。
実際に機器を搬入してみると、設置が難航し、導入後のオペレーション効率も下がってしまった。顧客側からは「現場を理解していない」という厳しい評価が下され、次の発注は競合に移ってしまった。業者向け製品であれば、現場との擦り合わせや運用環境の違いに対する理解の深さ、すなわち「目に見えないニーズ」への感度が問われる。現場で交わされる何気ない会話の中にこそ、大きなヒントが潜んでいる。気づき力とは、こうした「雑談の中の重要情報」を聞き逃さない感性でもある。

■気づき力は、キャリアステージに応じて求められる内容が変わる
気づき力は、キャリアのステージによってもその求められる内容が変わってくる。
若手にとっての気づき力は、「なぜこの指示が出されたのか」「なぜこの工程があるのか」といった背景への関心が求められる。単に指示されたことを的確にこなすだけでなく、その意味や目的に目を向けることが、学習速度や応用力の差につながっていく。
ミドルマネジメント層では、気づき力はより複雑なものとなる。現場と経営、部下と上司の間に立つこの層には、上意下達の指示をそのまま伝えるだけではなく、現場の温度感や言いにくい本音をすくい取る“翻訳者”としての役割が求められるようになる。部下の態度、会議の空気など、部署内での小さな変化に気づき、対処できるかどうかが、チームの団結力やパフォーマンスに直結する。
一方経営層にとっての気づき力は、数字や報告書だけでは捉えきれない「静かな変化」に目を向ける力だ。たとえば、社員の離職が続いているとき、その背景にある組織文化のひずみや、マネジメント層の疲弊にどれだけ早く気づけるか。あるいは、顧客のニーズが数字の裏で微妙にシフトしている兆しに、センサーの感度を上げてキャッチできるかにある。とくに前線の社員と距離が遠くなりがちな経営陣にとっては、顧客と接点を持つ社員と関わりをもつようにし、彼ら彼女らを通じた顧客や取引先の動き、そこからの社会全体の動向を感じ取る必要がある。
気づき力は「見る」「聞く」「感じる」といった人間の五感的な受容力・感応力だけでなく、そこに対する「なぜ?」「もし?」といった問いによって改善や改良の実践力に変わる。言葉にならないものをキャッチし、それを価値ある情報へと昇華させるのだ。この目に見えないプロセスこそが、AI時代におけるビジネスの差異化要素であり、人間にしかできない仕事の本質である。
ではその気づき力をどうすれば磨けるのか。
次回は、その気づき力を磨く身近な手法を紹介する。
(2に続く)
参考
【書籍】●『気づく力』畑村洋太郎、高田明和、大前研一、カルロス・ゴーン ほか[PRESIDENT BOOKS]●『「気づく」とはどういうことか』山鳥重[ちくま新書] ●『一勝九敗』柳井正[新潮文庫] ●『鈴木敏文の統計心理学』勝見明[プレジデント社]●『「気づき力」が組織を変える、仕事を変える―業務品質を高め成功要因を生みだすためのヒント』田中進[22 世紀アート] ●産業保健21 82 号 ●文部科学省「今、求められる力を高める 総合的な学習の時間の展開」 ほか
【WEB】●オージス総研「気づき力を高めるために必要なこと」/Exploratory「気づき力─意思決定の精度を上げるための3 つの提言」●「アンケートハガキを毎日1000 通読む! “ 超現場主義” 現場に成功のカギがある」(お店ラジオ)アキナイLABO ●トヨタエンタープライズ「トヨタ式研修の強み─カイゼン」● OJT ソリューションズ「トヨタの危険予知訓練「4RKYT」とは?危険予知能力を高める重要性も紹介」 ●資生堂 ● Panasonic「Switch Times」 ●セブン- イレブン・ジャパン ●日本の人事部 ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム