追悼 48億円企業から5兆円企業に育てた「中小企業のおやじ」鈴木修さんの「オサム主義物語」
昨年のクリスマス、日本を代表する自動車・二輪メーカーのスズキのトップを長年務めた鈴木修さんが、94歳で他界した。1978年に社長に就任してからは、社長や会長などを続け亡くなるまで48年、約半世紀にわたり代表取締役を続けた。
入社当時、年商48億円だった企業を、5兆円を超えるグローバル企業に育てながら、終生「中小企業のおやじ」と自称してきた鈴木修(以後修)さん。その気骨ある姿勢と危機に際してもユーモアで返す懐の深さは、日本の中小企業が世界で生き残っていくための手本を示してくれた。その修さんが生涯にわたって抱いてきた「オサム主義」の物語を辿ってみる。

目次
■売上高5兆円超。国内4位につけるグローバル企業「スズキ」
日本は世界に冠たる自動車メーカー大国である。量的には中国やアメリカには及ばないが、1億2000万人の人口の国でトラックメーカーを含めると主な会社だけで10数社、新興中小のEVの小型モビリティを含めると20社を超えるメーカーがひしめいている。そのうち1兆円以上の売上を誇るのは(2024年)11社。スズキはそのなかで4位に位置する。2024年3月期は5兆3743億円。初の5兆円超えとなった。押しも押されもせぬ大企業である。
しかしながらそのトップを半世紀近く務めてきた修さんは、自社を「中小企業」と呼んで憚らなかった。5兆円の企業を中小企業と呼ぶのは修さんの謙遜とも度重なる危機が襲った自社に対する自虐とも受け取れるが、本人は終生そう思っていた模様だ。なにせ修さんがスズキに入った時はまだ年間売上高48億円の会社だったのだから。
トヨタと同じ自動織機メーカーから転じて二輪メーカーとなったスズキは、修さんが入社した時、ようやく四輪を手掛け始めた頃で、いつ潰れてもおかしくない状況にあった。
スズキは二輪メーカーとして業績を伸ばしていたが、常にホンダとヤマハの二大巨頭の陰に隠れる存在だった。しかしホンダが当時世界最高峰の二輪レースであったイギリスの「マン島TT」など、国際レースで優勝を重ねると、スズキも参戦。ホンダの後を追うように優勝を続けていくと、ホンダに次ぐ2位の売上を誇るようになった。
■二輪メーカーから四輪メーカーへの脱皮に二の足を踏んだ2代目社長
売上が伸び、手元資金が増えたスズキは、創業者である鈴木道雄さんの悲願であった四輪事業に本格的に乗り出す。1955年、スズキは2サイクルエンジンFF(フロントエンジン・フロントドライブ)、360CC2ドアの「スズライト」を発売、日本の軽自動車市場の先鞭をつけた。スズライトの発売後、航空機事業を祖業に持つ富士重工が“てんとうむし” の愛称で人気をとった「スバル360」を、コルク製造機を祖業に持つ東洋工業(現・マツダ)は「R360クーペ」を発売し、日本の軽自動車市場は発展期を迎えた。
スズキが二輪メーカーとしての確固たる地位を築いた時、社長は道雄さんの長女婿である俊三さんになっていた。俊三さんは四輪を事業の主軸にすることには反対だった。せっかく二輪で稼げるようになったのに、難易度の高い四輪に挑戦して失敗するリスクを負う必要はないと考えていたからだ。エンジニアであった俊三さんはそのハードルをしっかり捉えていたのだろう。スズキの社内でも四輪事業については否定的な声が圧倒的だった。しかし国際レースで磨き上げられた2サイクルエンジンはスズキの技術力の賜物であり、スズキはこのエンジンを活かした軽自動車の開発を商用車で続けた。俊三さんは日本の所得水準や道路事情を見据え、軽市場は拡大すると睨んだのである。何より、スズライトの3年後に発売されたスバル360が空前の人気を誇ったのがその証だった。そして誕生したのが空冷2サイクル3気筒FFの2ドアセダン「スズキ・フロンテ」だった。フロンテは後の軽のスズキの代名詞ともなる名車「アルト」の原型となった。
修さんが入社したのはそんな時だった。
■“婿養子下ろし”に敢然と立ち向かった修さん
俊三さんは娘婿をとりたいと考え、ふさわしい人物として当時のスズキに出入りしていた中央相互銀行(現・愛知銀行)行員だった修さんに声をかけたのだった。「泥臭い営業をする元気のいい若者」が俊三さんの修評だった。1958年、修さんは婿養子としてスズキの創業家に入る。
入社後、研修として配属されたのが二輪工場だった。当時スズキは上場していたが、銀行員であった修さんからすれば、経理や在庫管理はいい加減で、材料や部品はしょっちゅう欠品し、製品の納期は遅れていた。工場にベルトコンベアはなく、町工場の延長のような現場だった。
にもかかわらず現場から上がってきた報告は、実態を反映しない“化粧されたもの”だった。修さんは「この会社は大丈夫か」と思ったという。
修さんへの風当たりも強かった。戦後の民主主義が浸透するなか、労働組合法が成立し、労働者の団体交渉権、ストライキ権が保証され、経営者と従業員の位置に差がなくなっていた。会社は社会の公器であり、「鈴木一族が世襲するのはいかがなものか」という空気が企業内に溜まっていった。
修さんへはさまざまな嫌がらせやトラップが仕掛けられたという。当時最大の仕掛けは、修さんが企画室の命を受け伊勢湾台風で大被害を受けた四輪工場の建て直しを担当することだった。約3億円の新規投資プロジェクトだったが、企画室のトップは予算オーバーになると予想し、修さんの失脚と一族の責任追及を目論んでいた。だが修さんは銀行マンとしての無駄削減のセンスを発揮、泥臭い営業力と懐の深さで建設業者との信頼関係を築いて、最終的に1割の予算を残してプロジェクトを完成させた。修さんは企画室に精算書を持って乗り込み、造反者を会社から追放させたという。
■社長就任前後、立て続けに会社存亡の危機がスズキを襲う
その後、俊三さんの義理の弟に当たる鈴木寛治郎さんが3代目社長に就任。寛治郎さんは引き続き軽を四輪事業の柱として展開していった。しかし1974年に施行された厳しい排ガス規制への対応に失敗。スズキは倒産の危機に直面する。1977年、寛治郎さんは65歳で脳梗塞に倒れ、翌年の78年に社長の座を修さんに譲ったのだった。
スズキの危機は創業以来幾度となく訪れているが、修さんの社長就任前後はまさに危機の連続だった。原因のほとんどが外部環境の大変化によるものだった。
1つは1971年に起きた「ドルショック」。当時のアメリカのニクソン大統領は、膨れ上がるドル需要に対して従来行われていた金とドルの交換を禁止、ドル相場が急落して日本経済に大打撃を与えた。さらに1973年に起きた第1次オイルショックによる原油の高騰と物不足による狂乱物価で、高嶺の花であった自動車需要は激減した。燃費のいい軽乗用車も例外ではなく、当時は「軽乗用車の時代は終わった」と囁かれ、1974年にはホンダが軽乗用車製造から撤退を余儀なくされた。年間の販売台数はピーク時の半分以下になった。
さらに1973年に産業界のご意見番たちが集う「産業計画懇談会」が、軽乗用車制度の廃止を政府に進言したのである。軽乗用車一本足打法だったスズキにとっては、まさに存亡に関わる出来事だった。
さらに当時米国できわめて厳しい排ガス規制「マスキー法」が1970年に施行されると、環境省の前身である環境庁はこれに準ずる排ガス規制を国内に導入した。寛治郎さんを苦しめた規制だった。
多くの自動車メーカーは4サイクルエンジンでの突破を図った。しかし、スズキは磨き上げた2サイクルエンジンで唯一規制を乗り越えようとする。排ガスを再燃焼させて有害物質を削減する「エピックエンジン」であった。
結局この規制は、業界全体の対応が難しいということで先送りが決定した。自動車業界はやや安堵したが、スズキにとってはさらなる問題が浮上した。1976年から軽自動車の規格が変わり、エンジン排気量が360CCから550CCに拡大され、車体寸法も全長が3.0メートルから3.2メートルに、全幅は1.3メートルから1.4メートルへと拡大することになったのだ。
スズキは劇的な為替変動と狂乱物価の嵐のなかで、2ストロークの新エンジンでの規制突破もままならず、また急な規格変更にも対応しなければならないという、どん底を経験することになる。この時、修さんが頼った人物がトヨタ自動車の社長で、自動車工業会の会長を務めていた豊田英二さんだった。修さんは英二さんに支援を要請し、頭を下げた。英二さんは、大所高所からの判断でダイハツの4サイクルエンジンを提供した。スズキの危機を救ったのはライバルのダイハツだったのである。
■度重なる危機のなかで誕生した初代「アルト」
修さんはなりふり構っていられる状況にはなかった。従業員とサプライヤー、その家族を守るために必死だった。そんな修さんを襲ったのが、相次ぐ鈴木家の指導者の他界であった。
1977年6月に岳父の俊三さんが亡くなり、同じ10月に創業者の道雄さんが病に倒れた。さらに11月に社長の寛治郎さんが65歳で脳梗塞に倒れたのである。
会社存続の危機に立たされた時、助言をもらうべき相手が次々と眼の前からいなくなってしまった。スズキの行方は修さん一人の両肩にかかったのだ。
修さんは「ワンマン」と称されることも多かったが、望んでワンマンとなったのではない。度重なる危機がそうさせた。一人で考えを巡らせ、一人で判断せざるをえなかったのである。
こうした危機の中で誕生したのが名車「アルト」だ。現在9代目となるアルトは、200万円超も珍しくない軽乗用車のなかで、自動ブレーキや、ふらつき防止機能、360度モニター、ヘッドアップディスプレイなど先進機能を装備しながら100万円以下の低価格を実現している。
アルトはスズキという会社の危機を救っただけでなく、スズキを軽ナンバーワン企業に育て、日本の軽自動車の概念を変えたクルマだった。
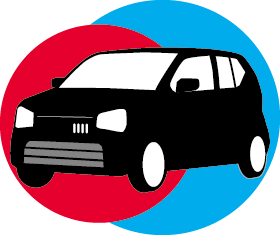
■商売にも使える乗用車、軽の「ボンネットバン」誕生
実はアルトの発売は1年延期されていた。修さんが従来の軽の延長でつくった軽では売れないと判断したからだった。修さんは自社工場を訪ね、通ってくる従業員に話を訊いた。そのなかに軽トラックの「キャリイ」で通ってくる人たちがいた。なぜキャリイで通っているのかと尋ねると「給料が安いから」と即答された。これには修さんも苦笑いをするしかなかったが、次に出てきたのが、「実家が商売をやっていて荷物を運ぶ」「農家をやっていて奥さんが使う」「雑貨を扱っているから」といった声があがった。軽トラックと乗用車があればいいが、「我慢して乗っている」というのだ。それでひらめいたのが、軽の「ボンネットバン」という新しい車の形態だった。
修さんはまたこんな声を聞いた。
自分の運転手がある時、隣のクルマをじっと見ていた。何を見ているのかと思ったら、「隣のクルマはスーパーデラックスですよ」と言ってきた。「社長、このクルマは安いです」と。修さんは「そういうところが気になるんだな」と思ったという。
それでアルトは、従来のスタンダードやデラックス、スーパーデラックスといったグレード分けをやめて、シングルグレードだけにした。
また価格設定も従来、地方別にかけていた運送費を乗せることを止めて、同一価格にした。全国同一価格というのは、ある種の“かけ”でもあった。結果的に販売先は東京・大阪圏が7割以上になり、北海道や九州・沖縄といった遠隔地は3割を切ったため運搬費分は十分カバーできた。現在当たり前となった自動車の全国統一価格はこのアルトに始まる。
■最初に「47万円ありき」。削って価格を出すスズキの「小・少・軽・短・美」
アルトの最大の特長はその価格にあった。
日本独自の規格である軽自動車は海外のコンパクトカーに比べても価格は安かったが、それでも当時の庶民にとっては高嶺の花だった。軽自動車でも1台60万円はゆうに超えていた。これは乗用車に15%の物品税がかかっていたためだ。
しかし商用車であれば物品税はかからない。修さんはそこに目をつけた。商用車と乗用車の両使いができる仕様の、「ボンネットバン」を考えたのである。
価格は50万円を切る47万円に設定した。50万円という数字は当時の中古車市場でよく売れる価格帯だった。
この価格はメディアの度肝を抜いた。常識ではありえないような価格を実現するために、修さんは役員や開発者を集め、ブレーンストーミングを重ねた。
修さんはとにかく47万円を実現するために、余分なものを削る提案を次々と出していった。「スペアタイヤを取れないか」「シートを外せないか」。挙げ句は「タイヤはなくてもいいのではないか」「エンジンを取れないか」とまで言ったという。
もちろんそんなことはできないと誰もがわかっていた。修さんは技術畑の人間ではない。でもその場にいた人間は誰も笑わなかった。皆修さんがわかっていて言っていることを知っていたからだ。47万円という価格は1円たりとも超えてはならない決定事項だった。それだけ切羽詰まっているということを、その場にいた人間は身に沁みて感じていたのだった。
スズキは経営理念となる社是の下に「小・少・軽・短・美」という行動理念を掲げているが、まさにアルトの開発が行動理念を体現していると言っていいだろう。パーツをできるだけ減らすために一体構造化できるものは一体化した。インパネや、シートとヘッドレストなどがそうだ。
ボディの外板の厚さも0.1ミリ単位で薄くしていった。ガラスも同様に薄くしていった。リアシートは折りたたみとし、素材には合板を使った。
スズキはこうして削れるものは徹底して削っていく。材料や手間、時間、コスト、無駄を1つ1つ省いていった。
この徹底ぶりは、後に自動車業界の巨人、アメリカのGM(ゼネラル・モーターズ)と合弁を組んだ時にGMから驚かれたという。
「我々は足し算しかしない。必要なコストを乗せ、そこに利益を乗せる。しかし、鈴木は削って削っていく。我々には削って価格を出すという発想はなかった。スズキのクルマづくりはアメイジングだ」
■生産設備は3年で減価償却
スズキの削る発想は経営にも反映されている。
たとえば、減価償却。スズキは生産設備を平均3年ぐらいで償却している。税法上の法定償却期間が10年となっている大型機械でも3年で償却する。それは中小企業としての経営発想があるからだ。
「我々のような中小は、大手のように10年単位で元が取れればいいというような悠長なことは言っていられない。いざ投資した後は是が非でも3年で元を取るという覚悟で皆一生懸命やる」
■軽自動車の一般的な重量から、150kg〜200kgも削減
アルトのためのブレーンストーミングは何ヵ月も続いた。もちろん価格を下げるだけでなく、乗る人の心地よさも追求した。特に室内の広さにはこだわった。
FFなので前のボンネットにエンジンルームが置かれるが、これを極端に小さくする。できるだけ車両の前方に出すように設計は何度も変更された。もちろんバンとして法的要件を満たすためでもあった。
こうして「小・少・軽・短・美」の理念を詰め込んだ初代アルトの重量は、540kgまで軽量化された。これは通常700kgから750kgが一般的だった軽自動車の重量を、150kg〜200kg近くも下回る。
■女性の社会進出を助けた「アルト」
こうして誕生したアルトの記者発表がまた絶妙だった。
アルトの名前はイタリア語で「秀でた」という意味だが、それでは伝わりにくいと思った修さんは、「ある時には〜」という話を持ち出した。「ある時は病院に」「ある時はお買い物に」。そういうたとえ話を続けたのである。修さんの当意即妙なアドリブであった。修さんは記者の前では「修語録」と呼ばれる非常にサービス精神にあふれるスピーチをすることで知られ、いつも記者発表では黒山ができるが、その頃からその才能は発揮されていた。
このわかりやすい事例は消費者の心を捉えた。当時は女性の普通免許取得が増え出した頃であり、通勤に使えるクルマとしてアルトは新しい女性層を開拓していった。
アルトは発売前の販売計画では月3500台が営業部の見立てだった。修さんは5000台は売って欲しいと伝えた。蓋を開けると月1万台が売れた。慌てて増産体制をつくるが売上はさらに伸び、販売台数は月1万8000台に達し、数ヵ月のバックオーダーを抱えるまでとなった。
アルトは優れた車だった。スズキの経営を確実に立て直し、会社にキャッシュフローを積み上げていった。その魅力はその後、1982年に進出したインドでも発揮された。
インドでスズキは「マルチ」という国営企業と合弁を組んで、国民車の開発に取り組んだ。アルトをスケールアップした800CCのセダン「マルチ800」である。だが記者発表で修さんは現地記者から辛辣な言葉を浴びせられる。「あなた方はこの街を知らない。モンスーンの季節にはこのクルマはデコボコの大きな穴にハマって姿が見えなくなるだろう」と。
だが、インド車や他の外国資本のクルマのなかで、モンスーンの激しい雨のなかで走り続けたのはこのマルチだけだったことを、後に地元記者は知るのだった。

■「光と重力」を存分に使った“修流”工場カイゼン
生涯「中小企業のおやじ」と言って憚らなかった修さんは、ケチケチイズムを車作りはもとより経営のいたるところで発揮した。
効率やカイゼン、無駄取りといった取り組みはトヨタが徹底していると思われているが、修さんのやり方もこれを凌駕するほどである。よく語っていたのが「光と重力はただ」という話だ。
スズキの工場では工場内の明るさを確保するため、大きな天窓をつけて、できるだけ外光を採り入れるようにしている。モーターやエンジンなどの動力も使わない。いわゆるカラクリ改善などを徹底させている。例えば長い工程を移動させるためにベルトコンベアに傾斜をつけて、動力を使わずに自重で運搬ができるように工夫をしている。
工場内のレイアウトもできるだけ直線的なものにし、動線を最短にして工程間バッファーを少なくし、工場面積を最小限に抑えている。このほか工場で発生する廃材を緩衝材として再利用している。
また部品の移送システムにおいては、モーダルシフトを進め、遠隔地向けに船舶による海上輸送を推進している。
こうしたスズキのケチケチイズムは、まさに現在のサステナビリティ経営に通じると言えるだろう。
■カタログ値より実燃費が高い「燃費不正」
しかも修さんの考え方は、自社生き残りだけの「ケチケチ経営」ではない。スズキの社是には「お客様の立場になって価値ある製品を作ろう」という文言が入っている。つまりお客様にとって価値ある製品のためのケチケチ経営なのである。
その考え方が如実に出たのが2016年の燃費不正問題である。
スズキは燃費不正を働いたということで、国土交通省から厳しい指導を受けている。燃費不正問題に関しては同時期に三菱自動車も起こしている。
三菱自動車と違っていたのは、その不正の数字が水増しではなく、逆に数字を下げて届けていたことだった。カタログ値より実燃費がいいのだ。
国交省が定める方式に則り、再度燃費測定をしたところ、対象となったすべての車種で燃費が上回った。正しく測定したら返って燃費が良くなったという話は前代未聞で、不正発覚後スズキの株価は一旦下落したものの、すぐ上昇に転じ、翌月には不正発覚前を上回っている。三菱自動車はこの不正で対象車が販売禁止となって社会的信用を落とした。経営危機に陥り、三菱グループを離れて日産グループの一員になったこととは対照的だった。
原因としては、スズキはより実燃費に近い欧州の測定方法を採用していたからとされる。修さんは記者会見で、「法令違反は違反である」とし、この問題発覚後CEOを返上している。
■軽ナンバーワンから、インドナンバーワンのスズキへ
修さんらしさが出たのは、日本のカーメーカーとしていちはやくインド市場に入ったことだろう。生来負けん気の強い性格で、トップに立つことに対して、とにかくがむしゃらに挑んできた。
軽ではライバルのダイハツとしのぎを削り、国内で長年トップの座を争ってきたが、販売シェアではスズキがほぼ王座を守り続けていた。
CMでは「軽ナンバーワン」が常套句となっていた。修さんにとっては軽のみならず、四輪全体で存在感を示したいと願っていたが、日本にはトヨタという世界ナンバーワンのメーカーがある。
そこで修さんが目をつけたのがインドだった。正確に言えば、スズキがインドの国営企業マルチ社に目をつけられた。当時インドでは低価格の国産車の製造普及が国家的課題としてあがっていた。
1982年にマルチ社のトップがパートナーを組む相手を探しに来日。修さんはマルチ社のトップと意気投合し、インドへの進出を決めた。その後、トヨタ、日産、三菱、マツダなどが現地で合弁会社を立ち上げたが、成功したのはスズキだけだった。
成功の要因は相手との信頼関係をしっかり持てたことだが、一番は設定した車体価格がインド市場にマッチしたことだった。他の日本メーカーの設定では高すぎた。修流ケチケチ経営がインドで花開いたのである。いまやインドにおけるマルチ・スズキの国内シェアは41%に達し(一時期50%を超えていた)、シェアナンバーワンである。

無論その道のりは決して平坦なものではなかった。まず文化や慣習の違いを克服しなければならない。特にインドではカースト制の根強い身分差が残っている。インドでは階級の違う人たちが日本の大部屋のように一つの場所で仕事をすることはまず考えられなかった。だが、修さんはインドでも日本のやり方を徹底した。日本のやり方や文化を説明する映画までつくって、日本のものづくり、スズキのものづくりを染み込ませていった。
またマルチ社は政府系企業であるため、政府や議会の影響を受けやすい。生産台数や生産する車体サイズなども、調査なしに決めてきたこともあった。それでもスズキは柔軟に対応し、結果政府が計画した年間10万台を超える12万台を初年度に受注した。
あまり報じられていないことだが、マルチ・スズキは2012年にインドの工場で激しい暴動に遭っている。待遇に不満を持った組合員、および社員約1000人が一斉に工場を襲い、放火され、死者まで出たのである。警察は暴動に参加した160人を逮捕した。修さんは暴動直後にインドに飛び、けがをした社員96人に直接会って激励した。マルチ・スズキは暴徒化した社員を映像や証言から特定し、解雇した。組合は解雇された社員たちの再雇用を求めたが、修さんは「あなたたちは、殺人犯といっしょに仕事をするつもりなのか」と断固として認めなかった。
修さんはそして「今度の暴動で一体誰が得をしたのか。社員は怪我をし、操業が落ちれば収入が減る。会社は社会的信用を失い、部品メーカーは休業。ディーラーもクルマが売れない。犯人たちは刑務所の中で人生に大きな傷を負った。結局誰も得をしていない」と繰り返し、労使協調の意義を強調した。
暴動から2年後の2014年、スズキは全額出資のインドの四輪製造子会社「スズキ・モーター・グジャラート(SMG)」の設立を発表した。マルチ・スズキは四輪の製造台数を引き上げず、研究開発と販売網整備に集中することになった。生産はSMGが担い、生産したクルマをマルチ・スズキが買い取って販売する。分社によって役割を分けたのだ。
しかし、この案は同年施行された小口株主を保護する新会社法で一旦頓挫する。スズキがマルチの利益をかすめ取るのではと小口株主たちの反発を受けたのだ。だがグジャラート州出身のモディ首相が、マルチ・スズキの社長の説明を受けた後、会社法の改正案を提出し、事態が好転する。
危機を乗り越えるたびにスズキは強くなっていった。修さんはインドにおける自動車製造と企業経営に自信を深めている。晩年自動車業界アナリストの中西孝樹さんとの対談で、「将来的にはインドに本社を置くかもしれない。インド人がトップになる可能性もある」とまで話している。
■ケチケチ経営が新たな危機を招く
修さんのケチケチ経営は度重なる経営危機から生まれたものだったが、90年代ともなるとそのケチケチ経営が新たな危機の要因となっていた。
90年代、修さんの考え方は会社全体にすっかり浸透し、常にコストダウンを念頭においたクルマづくりが進められるようになっていた。だが、あまりにそのやり方が強固なものになってしまい、新しい発想や技術も生まれにくくなっていたのだ。
とくに新鮮なスタイルを求めるデザイナーや、新技術や素材を求める技術者の意欲が失われつつあたのは問題だった。
閉塞感が漂うスズキを立ち直らせたのが元通商産業省(現・経済産業省)の官僚だった小野浩孝さんである。小野さんは修さんが自らスカウトしてきた娘婿であり、いずれ社長に立つ人間として、修さんのみならず、周りの役員の信頼を集めていた。
■世界への飛躍拠点を整備した婿養子小野浩孝
小野さんはスズキの現状を見て、持ち前の分析力でスズキの問題点と戦略を練り上げ、どのようにすべきかをロードマップに落とし、役員会で説明した。
小野さんの基本的な考え方は長期的な成長ストーリーを明らかにして、それに沿った商品企画を実現していき、その上で高い目標台数を掲げ、サプライヤーを巻き込みながら日本、ヨーロッパ、アジア、中国の4極で生産の同時立ち上げを実施するというもの。この「4極立ち上げ」という考え方は、大手の自動車メーカーでもなかなか立案しにくい大胆なものだった。その世界戦略車が1400CCの「スイフト」であった。このスイフトは、初代発表後、小野さんが若手の有望なデザイナーをイタリアに送り込んでデザインを完成させ、2台目のスイフトとして世に送り出した経緯がある。
デザインと機能性を高めたスイフトは評論家やジャーナリストが選ぶ「RJCカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞、以後、スイフトをベースとした「SX4」、「スプラッシュ」というグローバルモデルを展開した。さらに「SX4」はイタリアの「フィアット社」、スプラッシュはドイツの「オペル社」にOEM提供するまでとなった。
スズキの社員はこの成果に自信を持った。日本の軽ナンバーワンカーメーカーから、軽以外の世界で評価を受ける四輪を提供するグローバルカーメーカーにステップアップしたことを実感していった。修さんだけでなく小野さんの長期視点に立った分析力と構想力、実現力を認め、次期社長になるのは間違いないと思われていた。だが2005年に小野さんが胃がんが見つかる。小野さんはすぐ切除手術に踏み切ると、退院後まもなく職場に復帰して、以前と変わらず精力的に仕事をこなしていた。しかし2007年、今度は膵臓がんが発覚、結局社長就任目前で他界してしまった。
修さんの目論見はここでも外れてしまった。

■後継者育成にエネルギーを注入し続けた20年
修さんは1990年代後半から経営承継実現のために様々な取り組みを行ってきている。2000年に戸田昌男さんを5代目社長に起用し、自分自身は会長兼CEOに就任した。ところが直後、戸田さんが病に倒れ、ほとんどの実権は修さんが握ったまま戸田さんが退任することになった。その後も7代目と決めた小野さんが育つまでの執行部の若返り策として津田紘(ひろし)さんを6代目社長に任命し、修さん自身は会長兼CEOとして人材育成に専念した。しかしこれも小野さんの逝去で頓挫し、2008年リーマンショックが襲ったのを機に修さんはまた社長への復帰を余儀なくされてしまったのである。
その後修さんは4人の副社長に代表権を与え、経営委員会を設置して集団で経営を行う体制にした。修さんはこの経営委員会の委員長に息子の俊宏さんを任命した。
そして俊宏さんが十分経験を積んだ2011年で社長交代を図ろうとしたが、修さんは先送りすることにした。
当時提携していたフォルクスワーゲン(VW)との間にあった提携解消のゴタゴタが国際係争に発展してしまったからだ。修さんは社長交代をこの仲裁裁判の結果が出てからにするつもりだった。2015年6月30日、スズキは副社長の俊宏さんの社長就任を発表した。修さんは会長兼CEOに就任した。修さんが望んだVWとの紛争の仲裁結果は出なかったが、もう待てないと判断したためだ。ただ見込みはあった。VWの会長が4月に失脚していたことだ。相手の経営陣の構成が変わることは、長引いた仲裁に動きがあることを示唆していた。
8月、仲裁裁判の結果がスズキに届いた。スズキにとって完全勝利に近い結果だった。これでVWの顔色を伺うことなく、スズキがスズキらしい未来を描ける。
■生涯現役のカリスマ経営者、クリスマスに旅立つ
修さんは決してワンマンで頑固な中小企業のおやじではなかった。
これといった人材がことごとく退任、死去することになり、あるいは事業承継のタイミングで外部環境が激変したため、直接指揮を執らざるを得ない状況に陥り続けただけだった。
裁判の結果が届いた日、積年の課題だった後継者問題にも目処をつけた修さんを記者たちが取り囲んだ。今後の去就についての質問が飛ぶと、修さんは一言。
「まったく考えていない」
白い髪と眉毛と人懐こい目をしたサンタクロースのようなカリスマ経営者は、2024年のクリスマスに生涯現役のまま永遠の旅路についた。94歳だった。
POINT
■スズキは売上高5兆円超。国内4位につけるグローバル企業
■社長就任前後に立て続けに会社存亡の危機がスズキを襲う
■商売にも使える乗用車、軽の「ボンネットバン」アルト誕生
■最初に47万円の価格を決めて削っていったアルト
■軽自動車の平均重量から、150kg〜200kgも削ったアルト
■アルトを生み出したケチケチ経営がインドで花開く
■ケチケチ経営が浸透し、新たな危機が生まれた
■グローバルスズキの立役者、修さんの婿養子小野浩孝さん
■後継者に不運が続いた修さん
■「重力と光」をタダで活用した修式工場経営
■85歳で会長に。生涯現役を貫く
■インドのモディ首相の信頼を得た修さん
■ワンマンではない、ワンマンにならざるを得なかった
参考
【書籍】●『スズキのインド戦略』 R・C・バガルバ/島田卓監訳[中継出版]●『オサムイズム』 中西孝樹[日本経済新聞社]●『スズキものづくりの原点 初代ALTOと鈴木修の経営』 牧野茂雄[三栄]●『俺は中小企業のおやじ』 鈴木修[日経BPマーケティング]●『やらまいか』(スズキ社内報)
【WEB】●スズキ● JETRO ●東洋経済オンライン ●朝日新聞デジタル●読売オンライン ●時事ドットコム ●浜松情報BOOK ●日経クロステック ●ダ・ヴィンチ ほか
ビジネスシンカーとは:日常生活の中で、ふと入ってきて耳や頭から離れなくなった言葉や現象、ずっと抱いてきた疑問などについて、50種以上のメディアに関わってきたライターが、多角的視点で解き明かすビジネスコラム